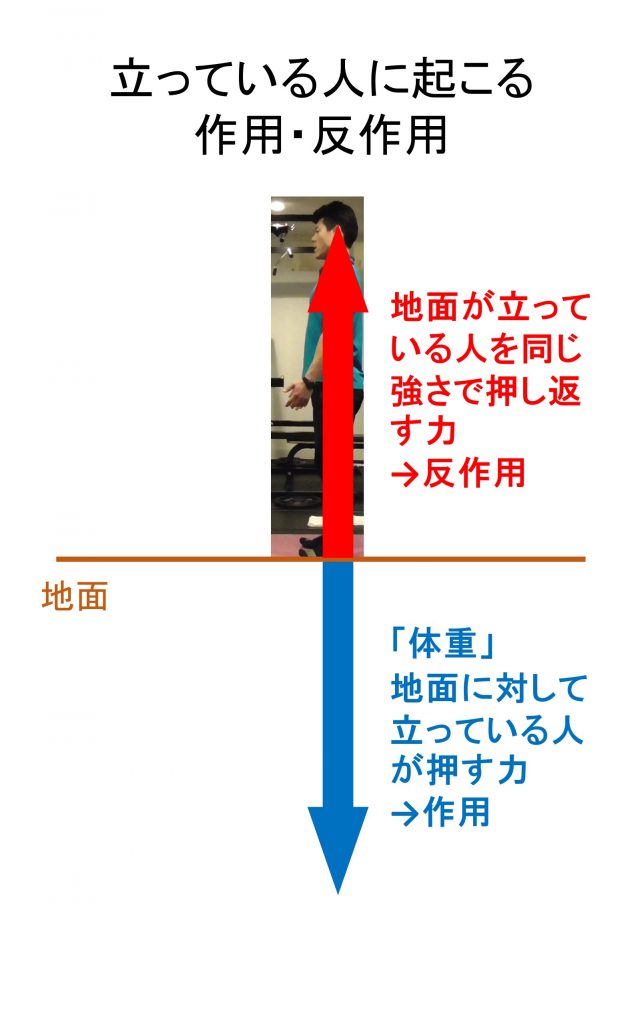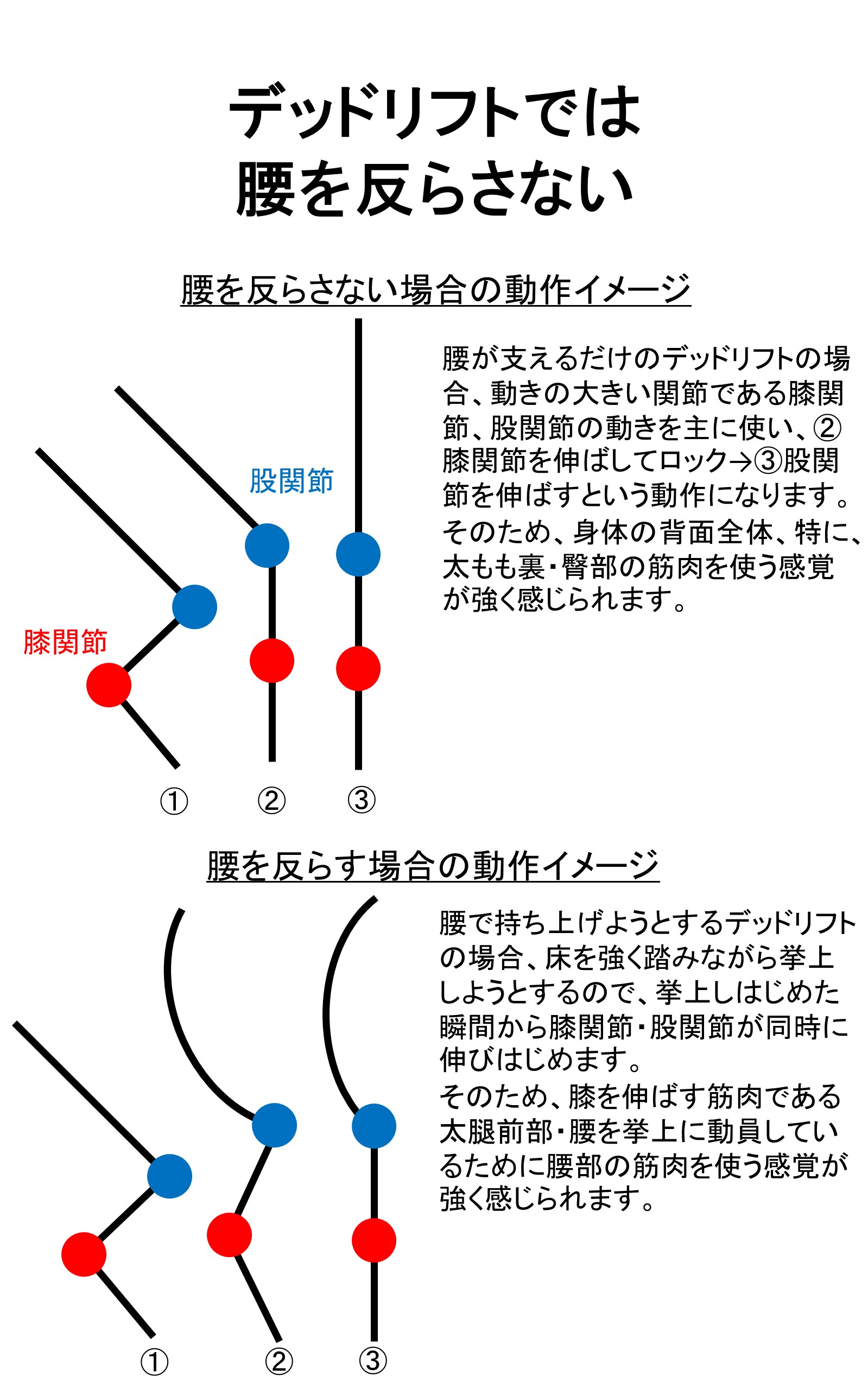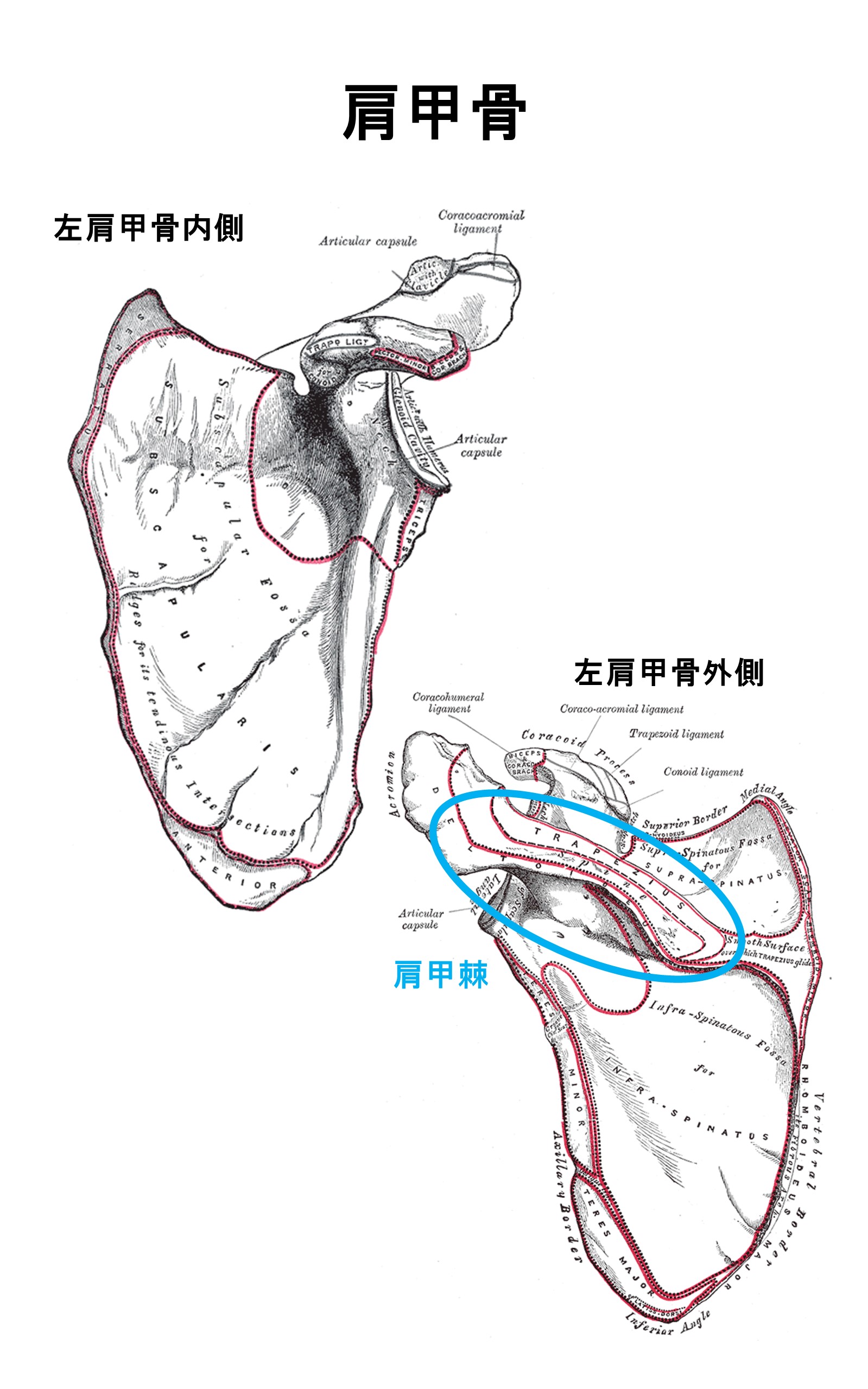トレーニング動作の範囲については、一応分類して呼ばれています。
●フルレンジ…基本的には、最大可動域のことをいいます。
トレーニングをする際、最大可動域を用いることで最大のトレーニング効果をあげることができると一般的には言われています。
筋肉をしっかり動かす、できるだけ多くの筋細胞を使えるからでしょうか。
ただ、常にフルレンジで動かすのは大きなリスクをともないます。
●パーシャルレンジ…部分的な可動域のことをいいます。
可動域いっぱいで動かせる(フルレンジで動かせる)にも関わらず、あえて可動域の一部だけを用いてトレーニングする場合にパーシャルレンジと呼ばれることが多いです。
基本的に、筋肉は負荷がかかればかかるほど、張力がかかるため(余力が少なくなるため)、可動範囲が狭くなります。
僕自身は、トレーニングのセットの中で、最初の余裕のあるうちはできるだけ、フルレンジで行い(スティッキングポイントは避けるようにする)、終盤のきつくなってきたときにパーシャルレンジに切り替える(自然とそうなる)みたいに、動作範囲を使い分けています。
僕は特にスポーツなどをしていないので、広い可動域を使ってトレーニングしておいた方が、身体を動かすという観点においては有用かなくらいの感覚でやってます。
前述のとおり、筋肉に負荷がかかるほど可動範囲が狭くなります。
もっといえば、発揮できる筋力が小さくなると、可動範囲が狭くなるのです。
たとえば、ベンチプレスで考えてみます。
セットの最初のうちは、バーベルを胸までしっかり下げることができるでしょう。しかし、だんだんと胸まで下げるのが辛くなります。
これは、ベンチプレスにおいて、いちばん筋肉が力を発揮しなくてはいけないポイントがバーベルを下げたときだからです。肘を曲げることで骨の積み木を崩し、筋肉で支える必要が出てくるからです。
そして、終盤では疲労するに従って、胸まで下ろせなくなってきます。最終的にはほとんど肘をまげることができなくなるでしょう。
そして、セットの最後、肘を伸ばした状態ですら支えるのがしんどくなってきます。ここまできて、ようやくセット終了です。
骨の積み木が積まれ、骨の支えがあってもなお力が発揮できない状態に追い込むように僕はトレーニングします。
以上見てもらったように、
フルレンジがいいとか、パーシャルが悪いとか、そんな話ではありません。
結局は、スポーツなど目的に即した形にした方が、トレーニングは活かされやすいので、きちんとトレーニングの目的を持つ、ということが大事だと思います。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。