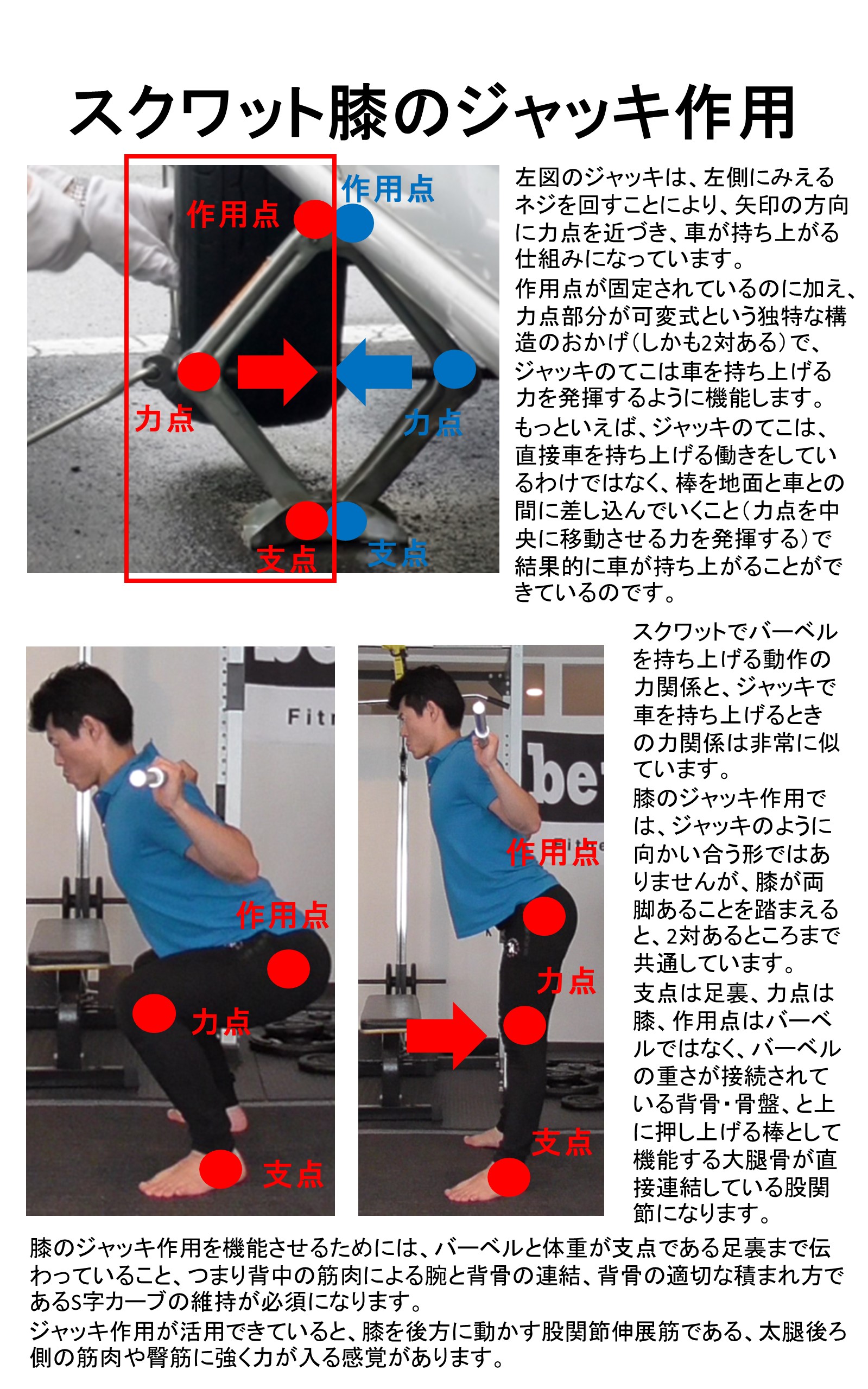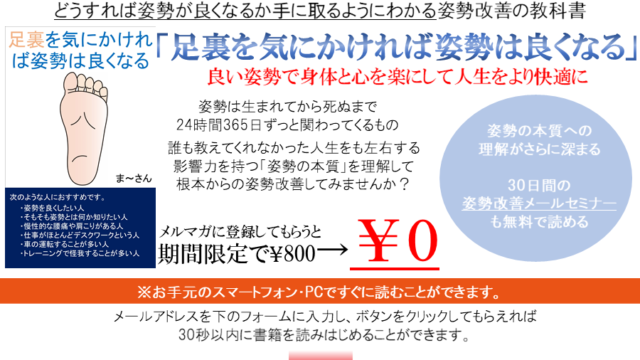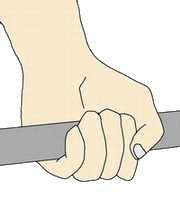アイザック・ニュートンがまとめた運動法則です。
これらの法則はさまざまな分野において活用されており、姿勢や身体の使い方はもちろんトレーニングにおいても、とても役立ちます。
学生のころに一度は習ったことがあるのではないでしょうか?
忘れてしまっているなら、ぜひこの記事を最後まで呼んでください。
ニュートンの法則は
慣性の法則、運動方程式、作用反作用の法則の3つあります。
以下それぞれ説明していきます。
●慣性の法則…ニュートンの法則の第1法則で、外から力が加わらなければ、一様な運動をする物体は一定の速度でその動きを続け(等速直線運動)、停止している物体は静止状態を続けるとする法則のことをいいます。
つまり、物体の動きは力が加わらない限り変化しないってことです。
たとえば、走っている電車はブレーキをかけられない限り、同じスピードでまっすぐ走り続けます(摩擦や線路、空気抵抗などは外から加えられている力です)。
また止まっている電車はアクセルが入れられない限り止まり続けます。
この法則は、それまでの力の概念を否定しています。
ニュートンが慣性の法則を提示するまでは、ざっくりですが力を加え続けないと物体を動かすことはできないと考えられることが多かったのです。
例えば、物を投げた時、その物にはずっと力が働き続けていると考えられていたのですね。
慣性の法則から考えれば、ピタッと静止したいのにできないということは、何らかの力が働いているので、それを相殺できなければ静止することができないと考えることができます。
●運動方程式…ニュートンの法則の第2法則で、物体に力が加えられると、その力と同じ方向に加速度を生じ、加速度の大きさは力に比例し、物体の質量に反比例するという法則のことをいいます。物体の質量が大きいほどそれを加速させるにはより大きな力が必要です。
一定の力が与えられたときに起こる物体の速度は質量が小さいほどその変化(加速度)が大きくなります。
たとえば、野球ボールとソフトボールを同じ力で投げた場合、野球ボールのほうが球速は速いですが、それはソフトボールに比べ野球ボールの質量が小さく、ある球速で投げるために必要な力が少なくて済むから、ということが挙げられます。
運動方程式は「力とは何か」を定義しました。
古い「力」の概念を否定し、新しい「力」の概念を提示する、ニュートンの法則はまさに物理学における変革期の一つと言えるでしょう。
●作用反作用の法則…ニュートンの法則の第3法則で、物体Aが物体Bに力を加えた(作用)とき、物体Bはその力と同じ大きさで反対方向に働く力を物体Aに与えているとする法則のことをいいます。
たとえば、ジャンプしようと足で地面をおもいきり踏むと、その踏んだ分と同じ力が逆方向、つまり踏んだ本人に与えられ、その結果ジャンプすることができます。
作用反作用の法則は、何かしらの力(作用)が働けば、それに対して反作用が働くということを指摘しています。
そして、地球上で生きている限り、我々は「重力」に作用される状態です。
つまり、我々には常に重力による「作用」とそれに対する「反作用」が存在することになります。
ただ地面に立っているだけでも、重力によって地面を押し、地面から同じ力で押し返されることで、力がつり合い、我々は地面のうえにじっと立っていることができるのです。
これがわかると、いろいろトレーニングにも応用ができてきます。
姿勢や身体の使い方、トレーニングやスポーツに至るまで、「力」をイメージできることが大切になってきます。
そのためにも、このニュートンの法則は絶対おさえておいてほしいところです。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。