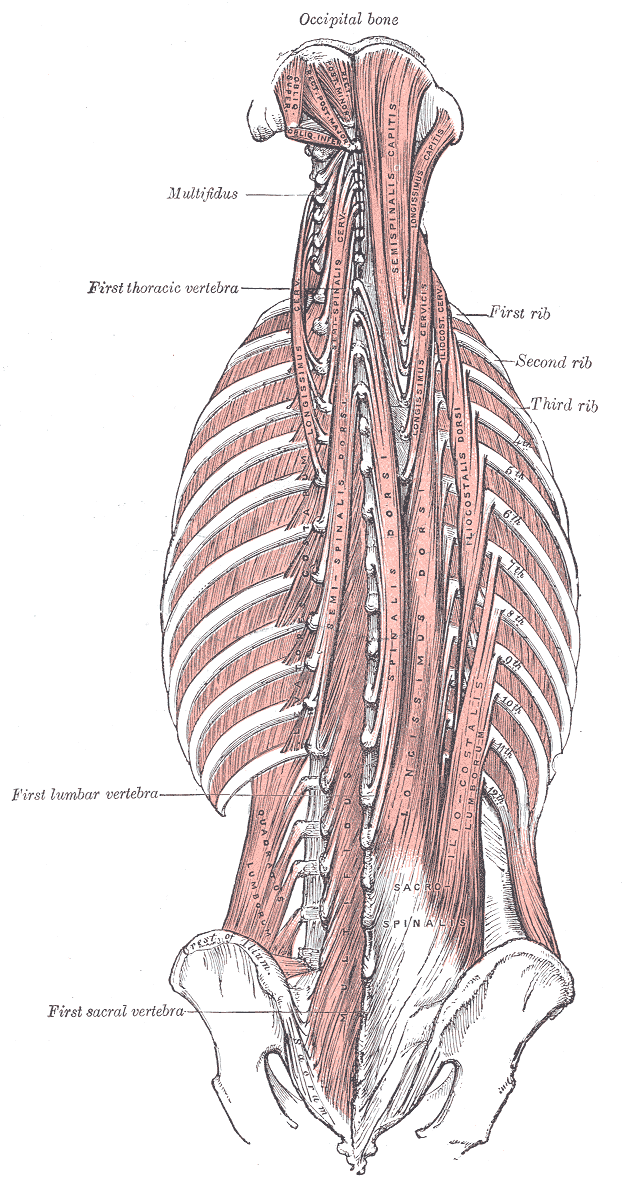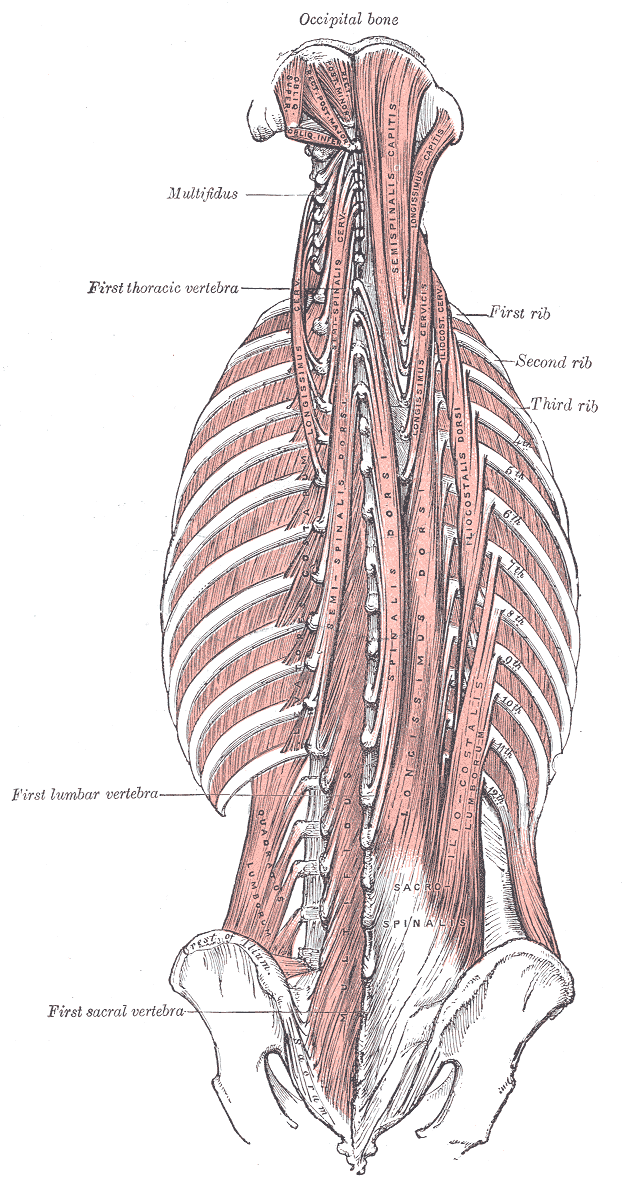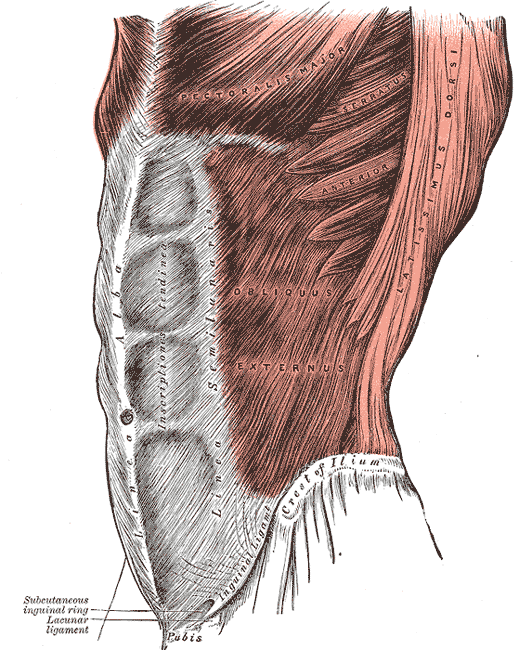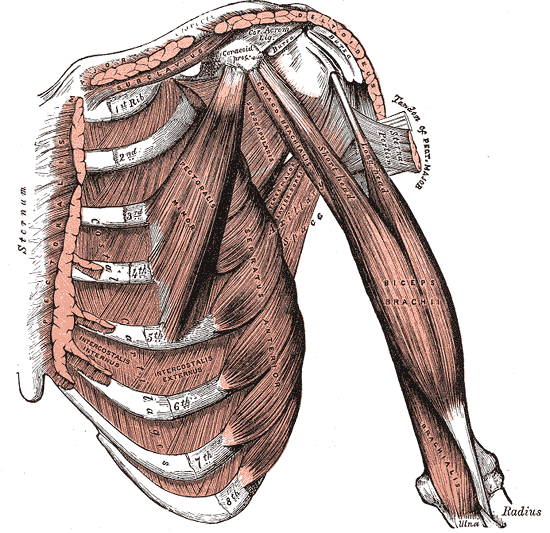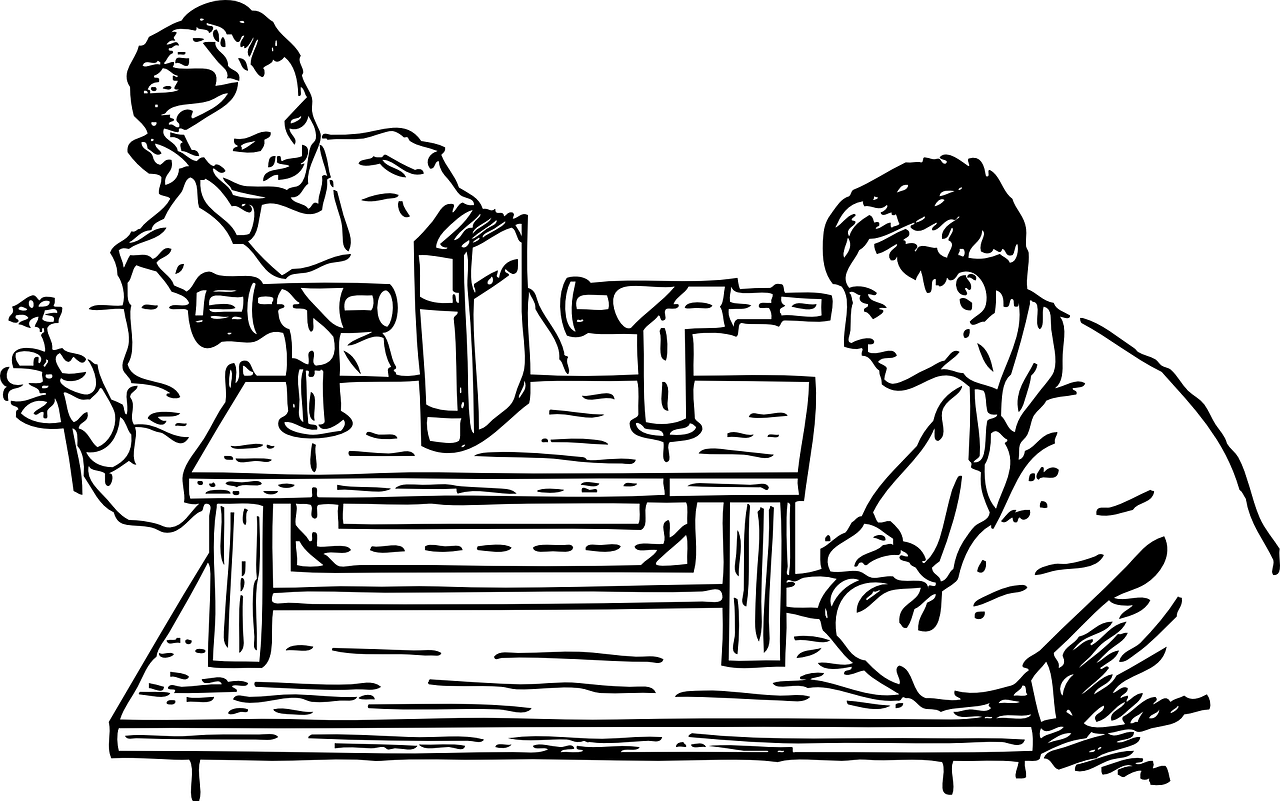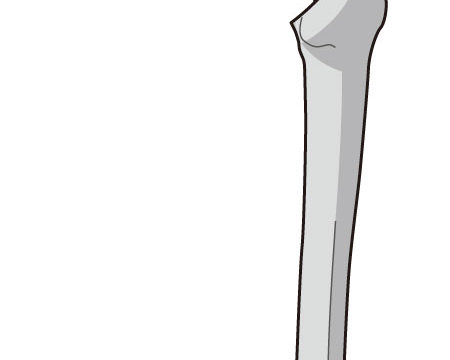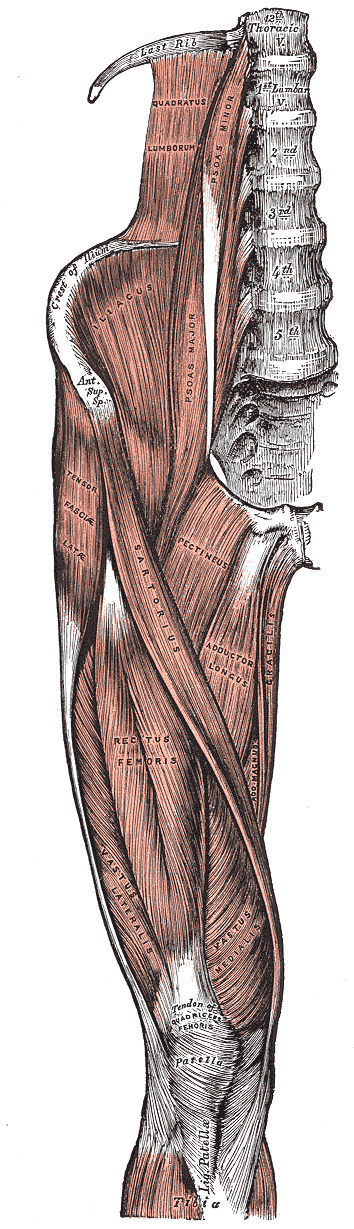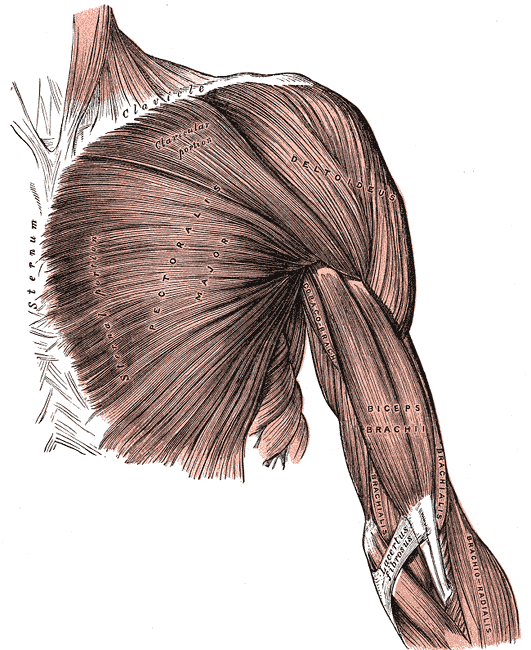フィットネスクラブでの大掛かりな機械を使った体組成の測定では、基礎代謝量を算出するものがあります。
最近は、家庭用のものでも算出してくれるものがありますね。
ただ、基礎代謝量とは何かを知らなくては、その数字も虚しく表示されるだけになってしまいます。
そこで、今回はこの基礎代謝量についてお伝えしていきます。
まず、定義的な話をしていくと、
基礎代謝量とは、体を横たえて全く体を動かしていなくても、呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つなど、様々な生命活動のために、常に使っているエネルギー量のことです。
言い換えると、「生きていくために最低限必要な最小のエネルギー」のことです。
基礎代謝は車で例えるとエンジンをかけた状態、アイドリング状態にあたります。
最近の車ではアイドリングストップ機能のある車が増えてきましたね。
そのような機能があるのは、アイドリング状態であるだけでも燃料消費が多いからです。
これは人間の身体も同じです。
人間でいうと生きていること自体がアイドリング状態なわけです。
すなわち、運動のことは考えず、アイドリング状態のみで消費されるエネルギーが基礎代謝量なのです。
小難しくいうと、基礎代謝量は、空腹時に安静仰臥位の状態で測定したエネルギー量、つまり、前日の夕食から12時間以上絶食した空腹状態の目が覚めた状態で仰向けの姿勢でのエネルギー量のことを示しています。
仰向けは地面との接地面が多く、姿勢を保つのにもほとんどエネルギーを使う必要がない状態です。
実は、人体の総消費エネルギーの60~70%が基礎代謝量です。
裏を返せば、基礎代謝量が増えれば、それだけカロリー消費が増えるので、痩せやすい身体であるということができます。
ちなみに、基礎代謝量に食事誘発性体熱産生は含まれません。
基礎代謝量の定義自体が空腹時に食事をしないことが挙げられるので当然っちゃあ当然なのですが。
この食事性体熱産生とは、食事後、数時間にわたっておこるエネルギー消費量の増加のことをいいます。
食物の消化や吸収に必要とされるエネルギーです。
食事のあとって体が熱くなって、季節によっては汗をかいたりしますよね。
消化吸収にエネルギーを使うと、一緒に熱も発生してしまうのです。
食事性体熱産生は、一日の消費エネルギー量の約7~10%を占めているといわれています。
基礎代謝量と食事制体熱産生を除いて考えると、実際に身体を動かしたりして消費するエネルギーは20%程度に過ぎないのですね。
まあ人により運動量が違うので一概には言えませんが、基礎代謝を高めることは本質的なダイエットになりそうです。
そんな基礎代謝は18歳をピークに減少し、40代以降は激減します。
だから、歳を重ねると痩せにくいといわれるんですね。
いかに年齢を重ねても基礎代謝を落とさないようにするかが、中年太りを防ぐ鍵になりますね。
基礎代謝量と似た言葉で、安静時代謝量(RMR=Resting Metabolic Rate)があります。
安静時代謝量とは、快適な室温の部屋で、座って安静にしている状態で消費されるエネルギー量のことで、基礎代謝量の約1.2倍とされています。
活動や食事などの影響によって、多少変動します。
静時エネルギー消費量(REE=Resting Energy Expenditure)ともいいます。
食事誘発性体熱産生(DIT)を含みます。
安静時代謝量は普通に日常生活を送るのに必要なエネルギーといったところでしょうか。
基礎代謝量との大きな違いは、食事誘発性体熱産生を含むかどうかだそうです。
基礎代謝と安静時代謝は似てますが、違うので、混合しないよう注意しましょう。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。