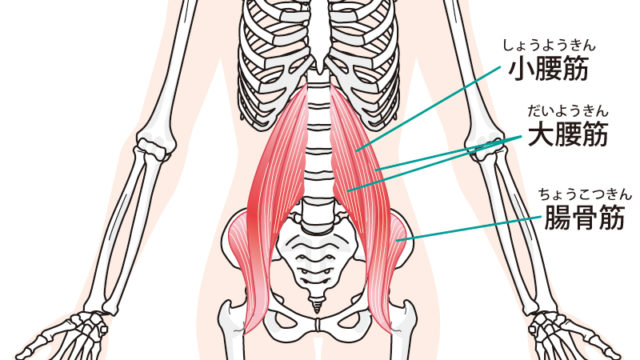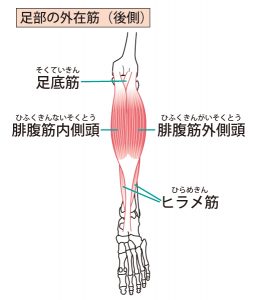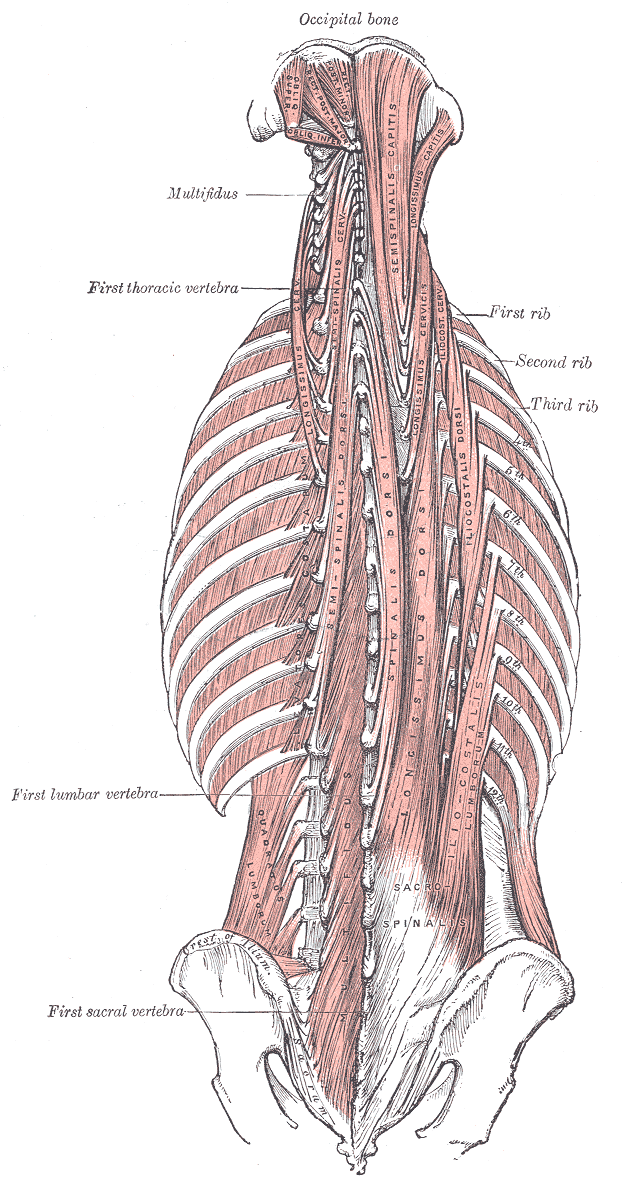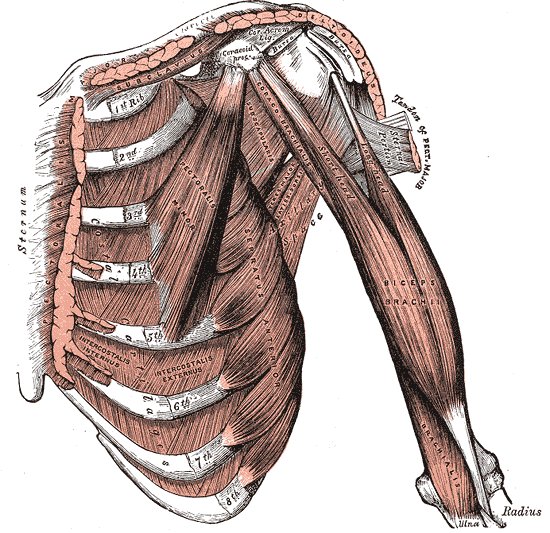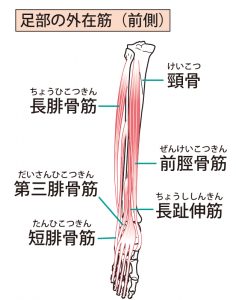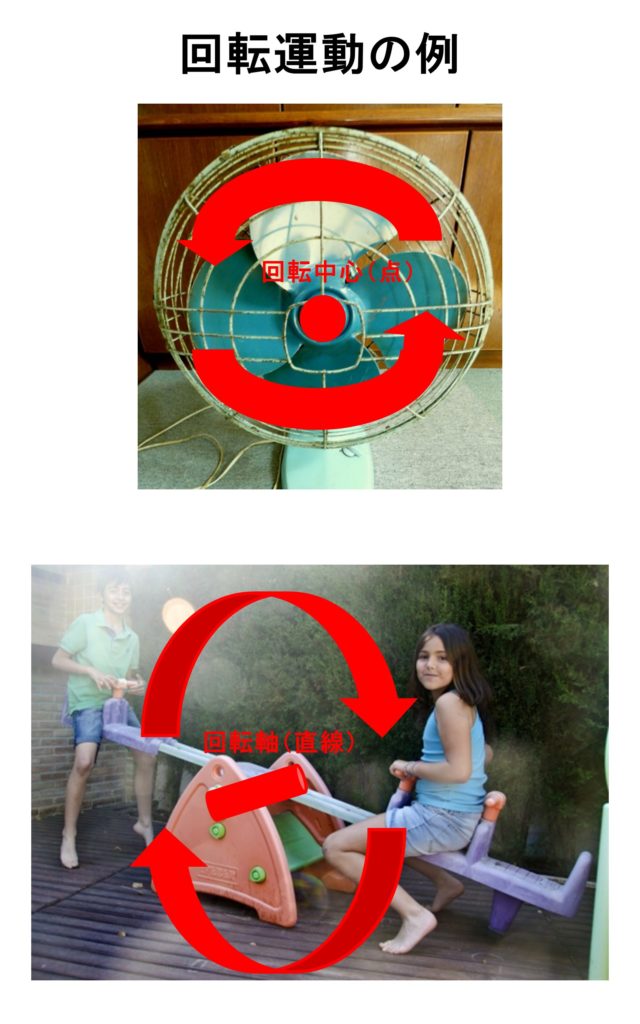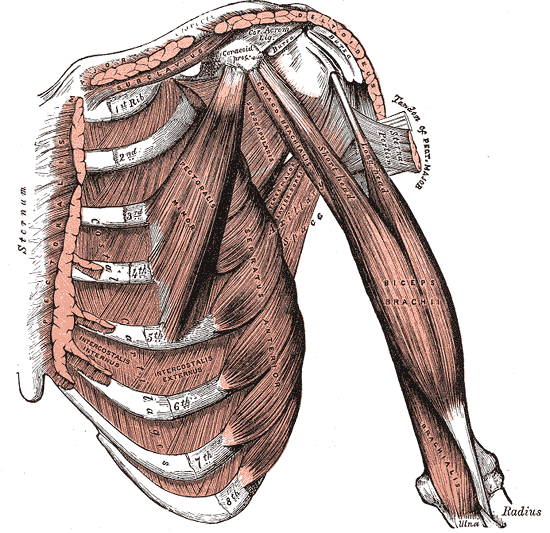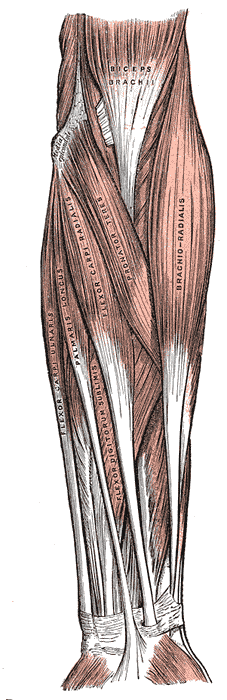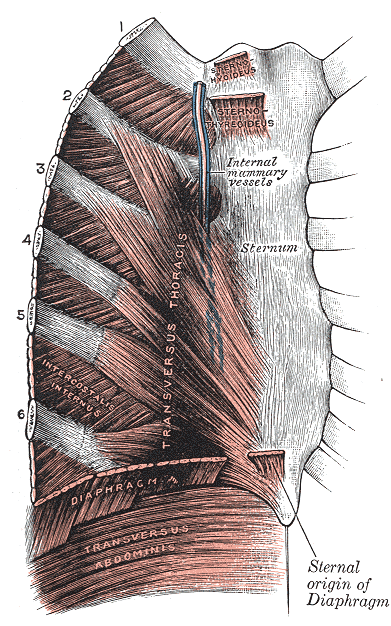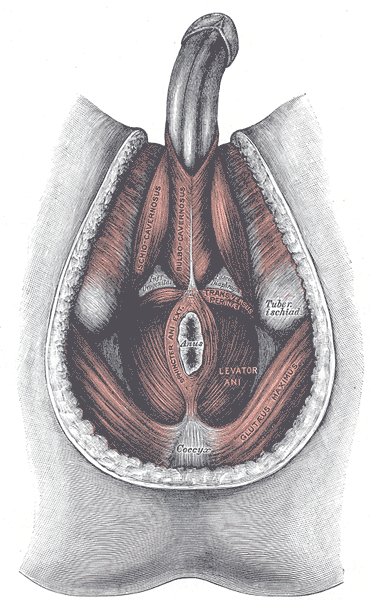横隔膜はおそらくほとんどの人が名前を聞いたことあるのではないでしょうか。
呼吸をするために絶対に欠かせない筋肉です。
「膜」という名前ですけど、筋肉ですよ。
横隔膜(Diaphragm)
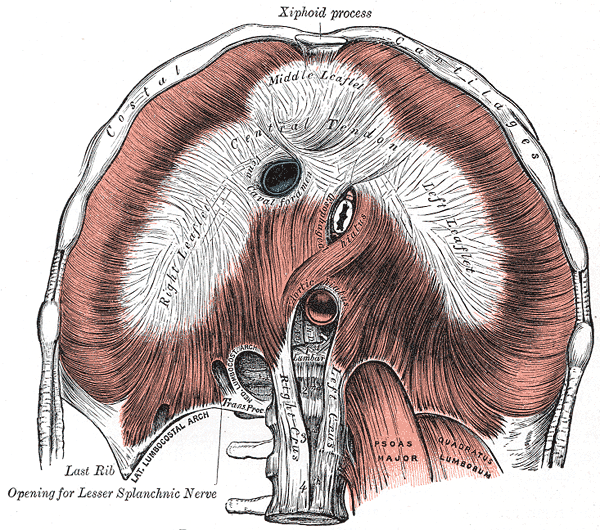
起始
・肋骨部:肋骨弓の下縁の内面(第7~12肋軟骨の内面)
・腰椎部(右、左脚)
→内側部:第1~3腰椎体、第2~3椎間円板、前縦靭帯
→外側部:第2腰椎椎体から肋骨突起の間に張る腰筋弓(内側弓状靭帯)、第2腰椎の肋骨突起と第12肋骨の先端の間に張る腰方形筋弓(外側弓状靭帯)
・胸骨部:剣状突起の後面
停止
腱中心(Central tendon)
作用
収縮によって胸郭を広げ、吸気を行う。また、腹腔内臓への加圧を助ける(腹圧負荷)。
神経支配
頸神経叢の横隔神経(C3~C5)
コメント
呼吸(横隔膜・胸郭呼吸運動)においてもっとも重要な筋です。腹腔上部にドーム状に存在しています。
息を吐くときのほうが力む感じがするので、横隔膜も吐くときに収縮していると思いたくなりますが、息を吸うときに収縮します。
横隔膜が収縮する時は、膜が下方に下がり、胸郭(胸をとりまく骨格)が広がります。
肺と胸郭の間には胸膜腔という密閉された空間があり、ここは大気圧より常に圧力が低い状態(陰圧)になっています。
そこで、先ほどお伝えしたように横隔膜の収縮により胸郭が広がると、胸膜腔の内圧はさらに低くなります。
すると、風船のような肺を外側に引っ張ろうとする力が働き、その圧力で、空気が肺の中に入り込むのです。
そうやって息を吸うことができるわけです。
外の空気の圧力が、圧力の低い胸膜腔に向かって空気を押し込んでくるようなイメージです。
ちなみに、横隔膜が弛緩して胸郭の容積が小さくなると、胸膜腔の内圧はその分高くなり、その圧力で肺は押しつぶされ、空気も押し出されます。
そうやって息を吐くことができます。
腹筋などが収縮して腹圧を高めるのも、胸膜腔の圧を高めるのに一役買ってますよ。
体内から外に向かって空気を押し返しているイメージですね。
わかりにくければ、注射器のシリンジでレバーのようなやつ(押子というらしいです)を押したり引いたりするところを思い浮かべてもらうとわかりやすいかなと思います。
この押子が横隔膜にあたります。
呼吸って不思議なもので、意識しなくても勝手にやってくれるし、意識すれば呼吸をコントロールすることができますよね。
いわば呼吸はセミオートマチックなのです。
これは、横隔膜が随意筋と不随意筋の両方の性質を持っていることに由来します。
ちなみに、随意筋とは自分の意思で動かせる筋肉のことをいい、不随意筋とは自分の意思とは関係なく動く筋肉のことをいいます。
ところで、なぜ呼吸がセミオートマチックになっているのでしょうか?
呼吸も生きるために必要なのだから、オートマチックでやってくれたほうが身体にとっても負担は少ないし、合理的なはずです。
思うに、これは呼吸が外部の状況に大きく左右されるからだと考えられます。
例えば、もし水の中で泳いでいるときに自動で呼吸してしまうと、水を飲んでしまって窒息してしまいますよね?
また、身体に害のあるガスが出ているとわかっていたならば、息を止めることができないと無防備に吸い込んでしまいます。
そういった選択ができるように、コントロールの余地を残しているんでしょう。
そして、呼吸は生存に必要な機能なのにコントロールの余地を残していることで、他の臓器や精神面などに意図的に影響を及ぼす可能性があります。
例えば、心臓の線維性の膜は、靭帯を介して腱中心に付着しています。
そのため、心臓は呼吸に合わせて上下運動しています。
つまり、横隔膜の動きが、直接心臓に影響を与えることができるのです。
心臓は酸素を含ませた血液を全身に送るポンプなので、酸素を取り込むための横隔膜と連結させておくのは、合理的なのかもしれません。
呼吸の話になってしまいましたが、横隔膜について少しでもわかってもらえたかなと思います。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。