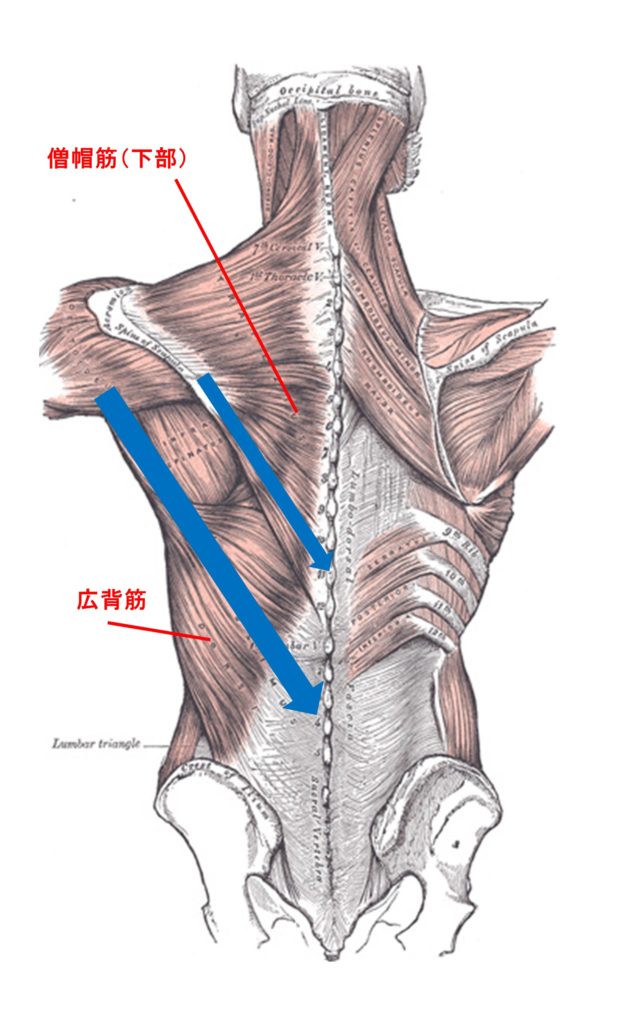よく武道のような身体の使い方を考える場面では、「骨で支える」という表現で伝えられることがあります。
でも、骨で支えると何で良いのでしょうか?
動物の多くの身体の構造は、骨の積み木を積み上げ、筋肉などによって崩れないように安定させています。
なので、骨がきちんと積み上げられていれば、それを安定させるための筋肉にかかる負担は最低限ですみます。
特に、人間の場合は4足を地面につけて過ごす多くの動物と違って、2本足で過ごすのが通常運行なので、より不安定な積み木になっています。
だからこそ、他の動物以上に「骨を積み上げて骨で支える」姿勢が重要になってきます。
ただ、骨はおもちゃの積み木のように、綺麗に積みあがるように形が整ったものばかりではありません。
場所によってはゴツゴツしていたり、水平ではなく斜めになっていたりと、複雑な積み上がり方をしています。
しかも、積み木自体は身体の表面からは見えない、自分では見えないところで積み上がっています。
そんな形が複雑で見ることもできない骨が、約200個もあるんだから、1個1個がいい感じで積み上がっているかどうかなんて認識するのは至難の技です。
でも、「骨がきちんと積み上がった状態」というものが何らかの形で認識できないと、何を目指して姿勢改善、骨の積み木の積み方の調整をしていくことはできませんよね。
どうしたら、骨が適切に積み上がったと自分で認識できるのでしょうか?

その答えは身体の底にあります。
立位の場合で考えると、身体の1番底は足裏になりますね。
積み木であれば積まれている1番下の積み木に重量がかかることになります。
上の積み木の重さも支えていることになりますからね。
試しに立ったまま床に向かって前屈し、骨盤から背骨をひとつひとつ積み上げるようにゆっくりおへそを見ながら上体を起こしてみましょう。
積み上げるごとにだんだん足裏が地面に押さえつけられるような感覚が得られるはずです。
であれば、足裏に着目すれば骨を積み上げた感覚がわかるのではないでしょうか?
詳細な説明は省きますが、実は骨の積み木が適切に積めているほど、足裏を重く感じます。
最も足裏を重く感じた状態、足裏が床に押さえつけられた感覚がある状態が、骨を積み上げ筋肉の負担を最小限にした良い姿勢です。
しかも、この足裏が重たくなる感覚は、同じ体重であっても姿勢次第で変化します。
その理由は足裏に対する圧力が関係してきます。
もし、ちょっと姿勢に興味がでた人は、ぜひ次の記事を読んでみてください。
【姿勢の理解】姿勢について、足裏の重要性、姿勢とトレーニングの関係性〜トレーニングは日常からはじまっている〜
姿勢改善の第一歩は腹筋背筋を鍛えることでも、胸をはるように意識をすることでもありません。
姿勢改善は姿勢を理解することから。
上の記事を読んでいただくと、姿勢の理解を深めてもらえると確信しています。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。