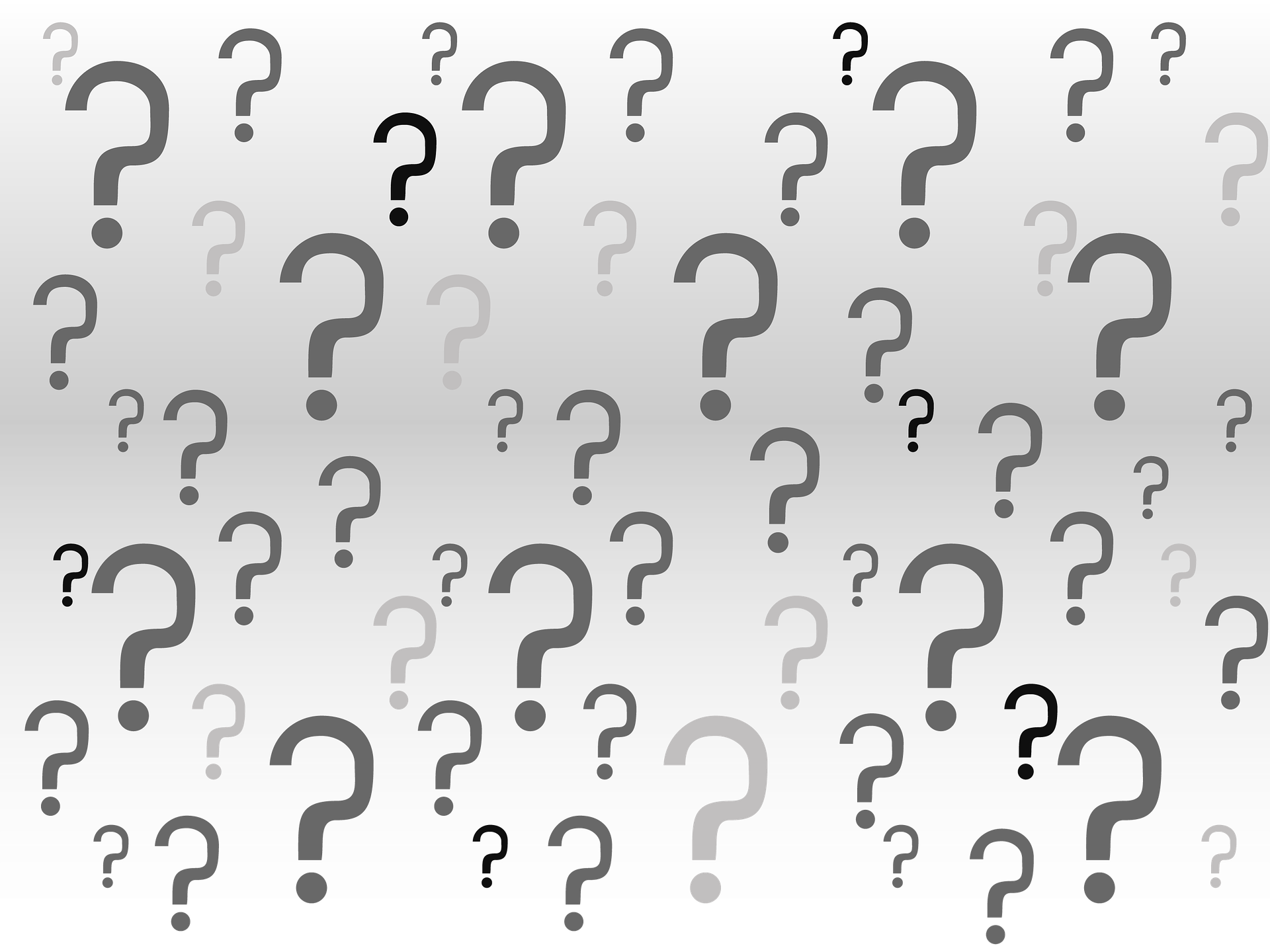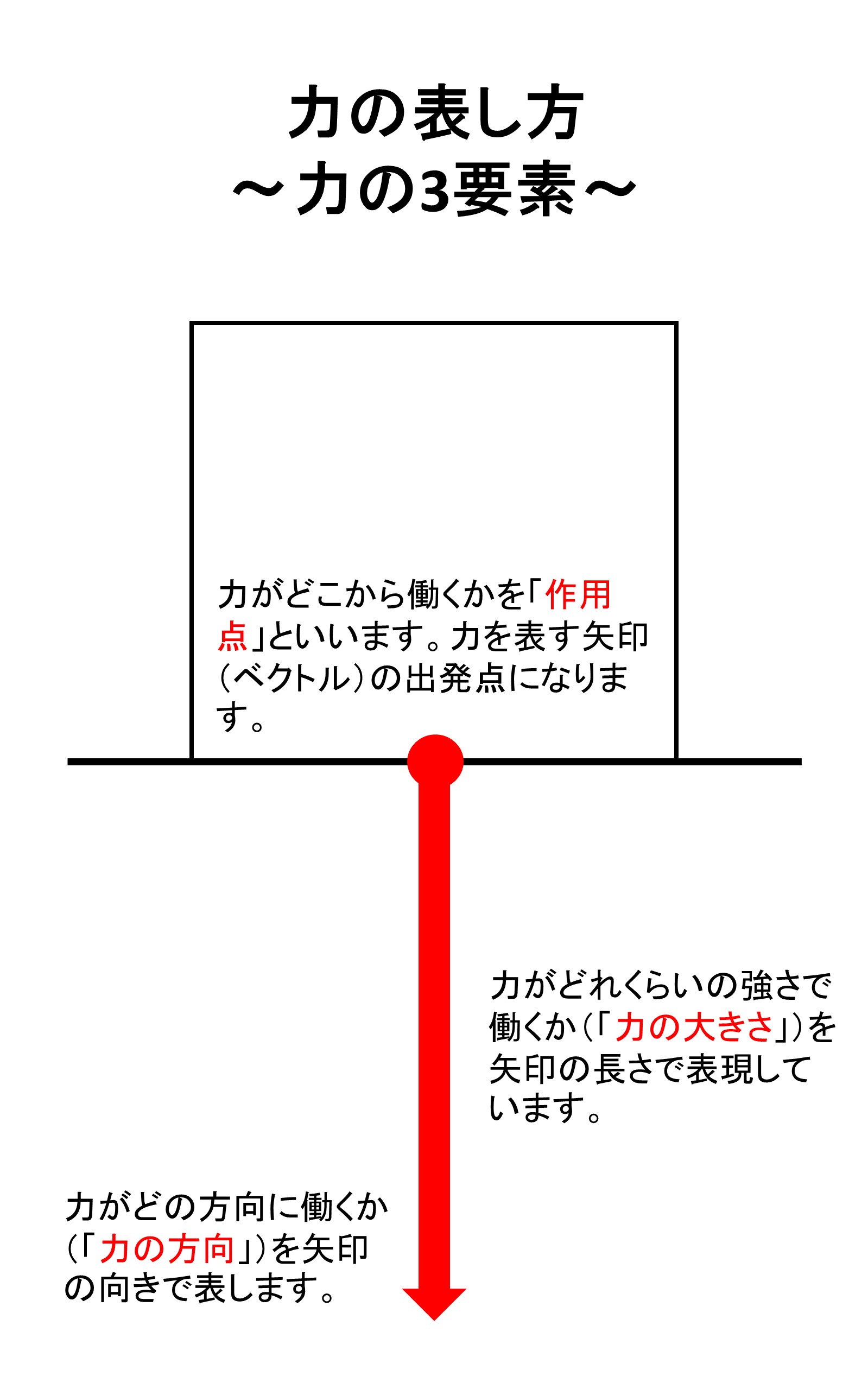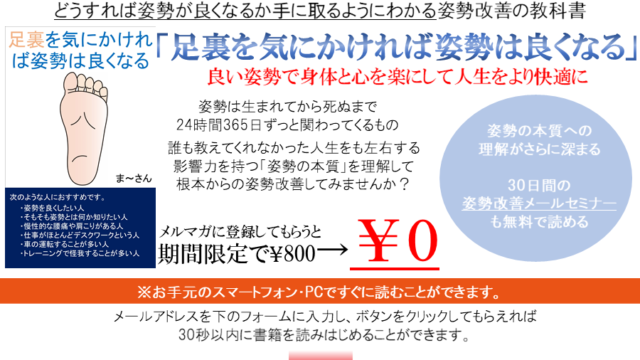人間は食べ物を食べて栄養を摂取することで生きています。
今回は、その栄養の中でも主たるもの、主要栄養素についてお伝えしていきます。
主要栄養素とは、食事で多くの量を摂取する必要がある栄養素のことをいいます。
主要栄養素とされる3つの重要な栄養素は、①タンパク質、②炭水化物(糖質と食物繊維)、③脂質(油脂および関連化合物)です。
タンパク質
タンパク質とは、炭水化物や脂質もそうなのですが、炭素、水素、酸素原子を含む化合物です。
化合物と聞くと難しく聞こえますが、いくつかの元素が合体したものと思ってもらえればいいです。
タンパク質が身体の中でどのような役割をしているかというと、血液や筋肉などの身体をつくる主要な材料となっています。
時にはエネルギー源になることもありますけどね。
炭素、水素、酸素原子を含むという共通項をもつ3つの栄養素において、炭水化物・脂質とタンパク質の違う点は、窒素原子を含むことです。
そんなタンパク質はアミノ酸分子が数十個から数百個結合してできています。
ちなみに、タンパク質は窒素原子を含むという話をしましたが、アミノ酸の「アミノ」とは「窒素原子を含有している」ことを意味しているそうです。
アミノ酸は自然界には数千種類も存在するそうですよ。
ただ、ヒトの体内のタンパク質は20種類のアミノ酸で構成されています。
ヒトの体内にある20種類のアミノ酸のうち、半数以上のアミノ酸は体内で合成することができ、食事で摂取する必要がありません。
このようなアミノ酸を非必須アミノ酸といいます。
まあ直接そのまま摂取する必要がないってだけで、合成するためには別に材料がいるわけです。
その材料は食べ物や呼吸から得ているわけなので、間接的には食事で摂取はしていますよ。
一方、体内で合成できず、食事から摂取する必要のある9種類のアミノ酸を必須アミノ酸といいます。
これらは体内で合成できないので、そのままの形で摂取する必要があるアミノ酸です。
ちょっとややこしくなりますが、
アミノ酸は複数のものが集まってタンパク質になっていますが、この集まり方はペプチド結合と呼ばれる結合の仕方になっています。
2つのアミノ酸が結合したものは、ジペプチド、3個以上のアミノ酸が集まったものはポリペプチドといいます。
ちなみに、ペプチド結合とは、アミド結合のうちアミノ酸同士が脱水縮合して形成される結合のことをいいます。
一般的には、アミノ酸が50個以上結合したものをタンパク質というそうです。
ポリペプチドの鎖が結合することにより、さまざまな構造や機能を持つ多数のタンパク質を形成します。
筋線維はタンパク質の存在する部位として挙げられることの多い組織です。
トレーニングしたらプロテインを飲むのは、筋肉の材料を補填するためです。
タンパク質は体内の多くの組織に存在していますが、組織のほとんどは水であり、タンパク質の含有量はさまざまです。
タンパク質の割合は、心臓や骨格筋、肝臓、腎臓の重量の20%、脳組織においては10%にすぎません。
タンパク質は、含まれているアミノ酸が身体が必要としている量として見合っているかが、その質を決めます。
良質タンパク質としては卵や肉類、魚類、家禽類、乳製品に含まれる動物性タンパク質が挙げられます。
1つ以上の必須アミノ酸が不足しているタンパク質(穀類、豆、野菜、ゼラチンなど)は低質タンパク質とされます。
植物性タンパク質では、穀類でリジン、豆類ではメチオニンとシステインの含有量が少ない傾向にあります。植物性タンパク質のうち、大豆タンパク質はもっとも質が高いです。
ある食品に不足するアミノ酸を供給できるタンパク質を補足タンパク質と呼び、補足作用を持つ食品の組み合わせ例として、豆と米、トウモロコシと豆、トルティーヤとリフライドビーンズ、ピーナツバターとパンが挙げられます。
一般的には、豆類と穀類を組み合わせると、必須アミノ酸を適切な割合で摂取することができるようです。
すごくややこしい話にもなってしまいましたが、ここからわかるのは、栄養を理解するためには、化学についてもある程度理解しないとならないということです。
他の炭水化物や脂肪でもそういう化学の話がたくさん出てきます。
僕は正直栄養学についての話は苦手なので、まだまだ勉強中です。
食事は栄養だけで全てを語れるわけではないですしね。
ちなみに、タンパク質はプロテイン(Protein)とも言います。
この言葉は、古代ギリシア語のProteios(プロティオス)に由来しますが、その意味は「第一なるもの、主要なもの」です。
それだけ大事なものとして認識されていたのですね。
炭水化物
炭水化物は前述のように炭素と水素、酸素から構成されています。
もっとざっくり見ると、炭水化物は体内に吸収されてエネルギー源となる「糖質」と、消化吸収されずエネルギーにならない食物繊維とに分けることができます。
なので、「炭水化物制限ダイエット」とか「糖質制限ダイエット」といった最近は食事制限によるダイエットが提唱されていたりしますが、この2つの制限は意味が違うことになります。
炭水化物は、構成する糖の数によって、単糖類、二糖類、多糖類の3つに分類されます。
それぞれ見てみましょう。
単糖類(グルコース、フルクトース、ガラクトース)は1つの糖を持つ糖分子です。
グルコースは数多くのより大きな糖の形成単位となります。
グルコースは、血液中を循環する糖として、また、細胞の主要なエネルギー基質として、さらに筋や肝細胞に蓄えられた多糖類のグリコーゲンとして体内に存在します。
グルコース単体では甘味はありません。
食品としては、スクロース(ショ糖)のようにほかの単糖類と結合して存在しています。
単離グルコースは、輸液やスポーツドリンクに使われていることもあります。
この形状はデキストロースと呼ばれます。
フルクトース(果糖)はグルコースと同じ化学式を持つが、原子の配列が異なるため、より甘く、異なった特製を持ちます。
はちみつの甘味はフルクトースに由来します。
フルクトースは、自然界で野菜や果物に存在する上、体内でほかの糖に比べてインスリンの分泌を引き起こしにくいです。
ガラクトースは、グルコースと結合してラクトース(乳糖)を形成します。
二糖類(スクロース、ラクトース、マルトース)は2つの単糖類が結合したものです。
スクロース(ショ糖、または砂糖)はもっとも一般的な二糖類で、グルコースとフルクトースからなります。
スクロースはほとんどの果物に存在し、サトウキビやビート(サトウダイコン)のシロップから結晶化されてブラウンシュガー、パウダーシュガー、が作られます。
ラクトースは哺乳動物の母乳にしか見られません。
マルトース(麦芽糖:グルコースとグルコースが結合したもの)は、主に消化時に多糖類が分解されて生じます。
麦芽糖はアルコールの発酵過程においても発生し、ビールに含まれる主要な炭水化物です。
多糖類は複合炭水化物とも呼ばれます。
もっとも広く知られている多糖類は、デンプン、食物繊維、グリコーゲンです。
デンプンは植物におけるグルコースの貯蔵形態です。
穀類、ナッツ、豆、野菜はデンプンの優れた供給源です。
デンプンは、エネルギー源として使用される前に、まずグルコースに分解されなければなりません。
食物繊維は、植物の細胞壁の構成要素であり、これも炭水化物の1つの形です。
セルロース、ヘミセルロース、βグルカン、ペクチンなどの食物繊維、そして、炭水化物ではない線維状物質(リグニン)は、一般にヒトの消化酵素で消化されず、便の量や水分含有量を増やし、腸内滞在時間を減らします。
一時的な貯蔵エネルギー源としてのグリコーゲンは、ヒトや動物の組織中には少量しか存在しません。
摂取する食品に多くは含まれず、筋や肝臓に入ったグルコースが、エネルギーとして代謝されなければ、グリコーゲンになります。
グリコーゲンのうち3分の2は骨格筋に貯蔵されており、残りは肝臓に貯蔵されています。
グルコースからグリコーゲンが生成される過程をグリコーゲン合成と呼びます。
肝臓は体組織のうちグリコーゲン含有量が最も多く、さらに炭水化物由来でない多くの消化の最終産物をグリコーゲンに変換することができます。
これを糖新生といいます。
さて、炭水化物で注意したいのは、食物繊維が含まれる点です。
「炭水化物は太る」というイメージがあるかもしれませんが、それは「糖質」の「取りすぎ」にあります。
食物繊維は、腸を綺麗にしてくれるなどなくてはならないものです。
腸は免疫に大きく関わるし、「第2の脳」と呼ばれるくらい賢い部分です。
脳内細菌は、身体の中にあるドーパミンの50パーセント、セロトニンの90パーセントを生成していると言われています。
ドーパミンやセロトニンは、脳に強く作用する脳内物質です。
ドーパミンは主に快楽を与え、セロトニンは安心感や幸福感を与えると言われています。
つまり、僕たちの身体については、腸内細菌たちの意思を反映しているともいえます。
いわば、僕たちは腸内細菌たちの住む家を提供する大家さんなわけですね。
住人と大家の関係を良好にすることが、健康な身体を維持するための秘訣です。
脂質
脂質は、炭水化物と同様に、炭素、酸素、水素原子を含みます。
ただ、脂肪酸鎖は酸素原子に対して炭素と水素の数が多いため、1gあたりのエネルギーも高くなっています。
たとえば、炭水化物とタンパク質が1gあたり約4kcalなのに対して、脂肪は約9kcal(体脂肪は約7kcal)です。
脂質という言葉は、脂肪よりも広い意味を持ちます。
脂質には、トリグリセリド(油脂…植物性の油と動物性の脂肪の両方を意味する)とともに、コレステロールやリン脂質といった脂肪化合物も含まれます。
脂質の中で重要なのは、トリグリセリドや脂肪酸、リン脂質、コレステロールです。
トリグリセリドは3つの脂肪酸とグリセロールの結合体です。
食品中や体内に存在する脂質のほとんどはトリグリセリドの形をとっています。
脂肪の体内における働きは、その一部が脂肪酸の飽和状態と関係します。
脂肪酸の飽和状態は、脂肪酸が結合している水素の数によります。
飽和脂肪酸は結合可能なすべての水素が結合している脂肪酸です。
不飽和脂肪酸は、本来水素が結合している場所に炭素原子が二重結合で結合しており、化学反応をおこしやすいです。
二重結合のない脂肪酸を飽和脂肪酸といいます。二重結合を1つ含む脂肪酸は一価不飽和脂肪酸、2つ以上の二重結合を含む場合は多価不飽和脂肪酸と呼びます。
大豆油、トウモロコシ油、ヒマワリ油、ベニバナ油は多価不飽和脂肪酸を比較的多く含み、オリーブ油、ピーナッツ油、キャノーラ油は一価不飽和脂肪酸を多く含んでいます。ほとんどの動物性脂肪と熱帯植物の油(ココナッツ油やパーム核油など)は飽和脂肪酸が多いです。
脂肪は体内で多くの役割を担っています。
ヒトのエネルギーの多くは主に脂肪組織として貯蔵されています。
体脂肪は断熱や臓器の保護、ホルモンの制御に欠かせないものです。
脂肪はまた、脂溶性のビタミンA、D、E、Kの運搬を行い、リノール酸(オメガ6)やリノレン酸(オメガ3)といった必須脂肪酸を供給しています。
これら2つの必須脂肪酸は、健康な細胞膜の形成、脳や神経系の適切な発達と機能維持、ホルモンの生成に不可欠です。
体内のコレステロールも重要な機能を持ちます。
細胞膜の構造、機能における重要な要素です。また、胆汁酸塩やビタミンD、性ホルモン(エストロゲン、アンドロゲン、プロゲステロン)やコルチゾールなどのホルモン生成に必要です。コレステロールは肝臓と超で合成されます。
まとめ
主要栄養素は、身体を構成し、動かすために必要な栄養素です。
だからといって、筋肉をつけたいからタンパク質をとる、といったような単純な話ではないようです。
人間の中には、いもばかり食べていても筋肉がつく人もいたりします。
これは、体内に取り込まれた食物を消化する過程で、腸内細菌がいもからアミノ酸を合成するからだといわれていたりします。
人間の身体は、まだまだ神秘であふれています。
栄養学をはじめ、さまざまなことを学ぶなかで、「身体」の真実に少しでもせまれたらいいなと思います。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。