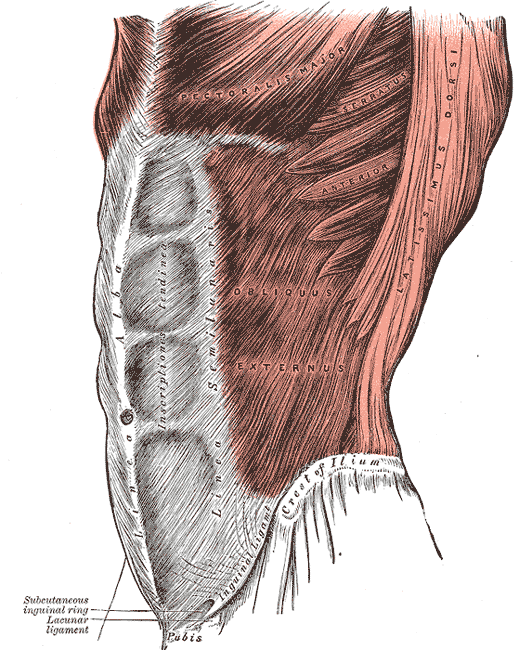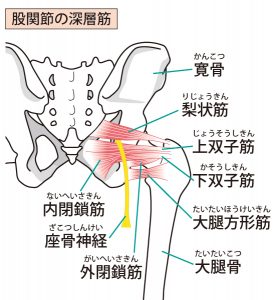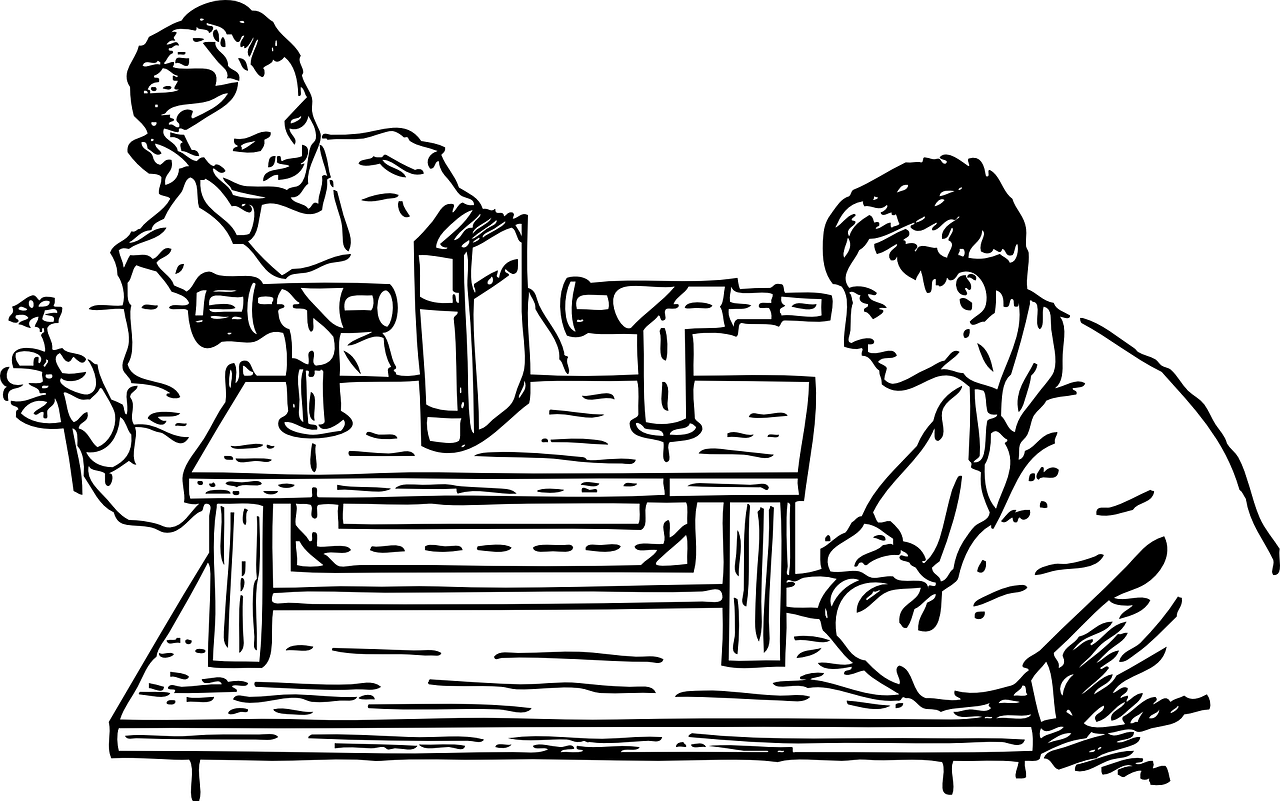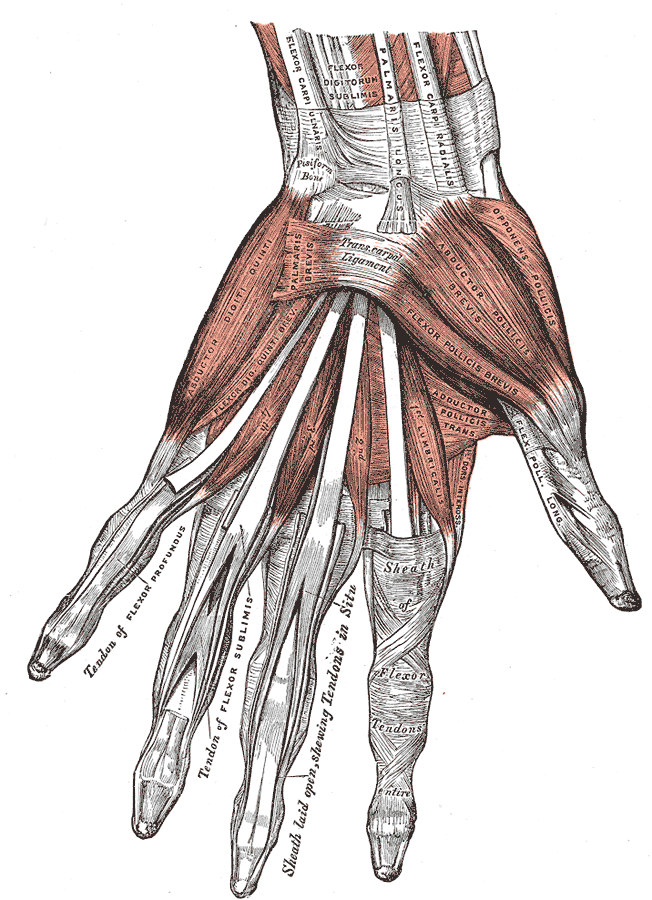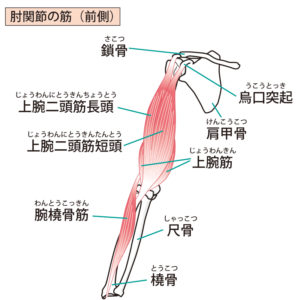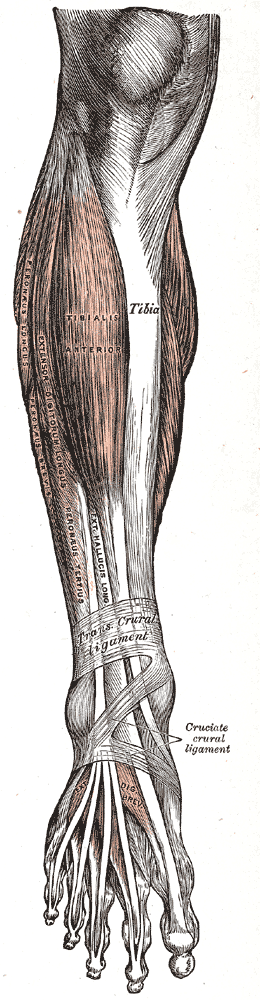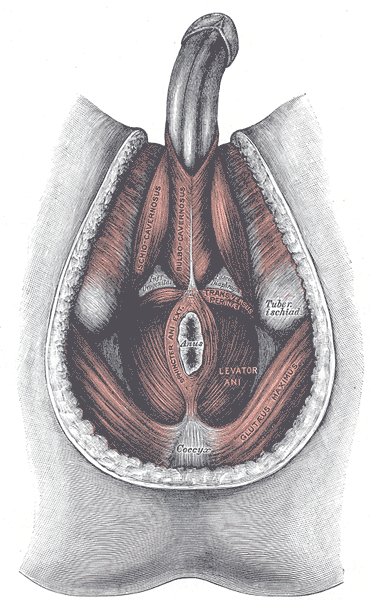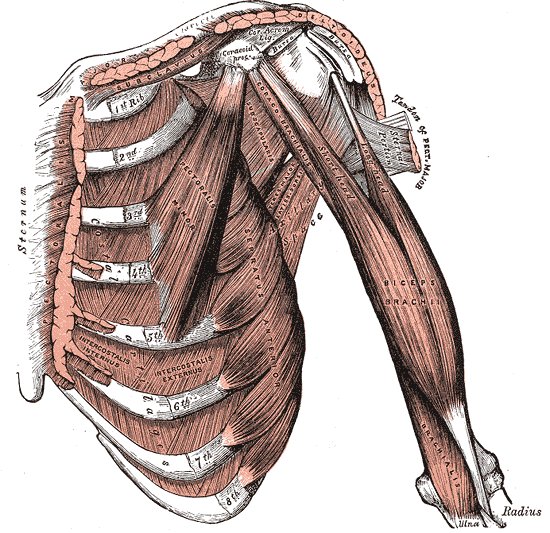前鋸筋は、あまり聞き馴染みはないかもしれません。
ただ、結構広範囲に付着してますし、役割も重要な筋肉です。
今回は前鋸筋についてお伝えします。
前鋸筋(Serratus anterior)
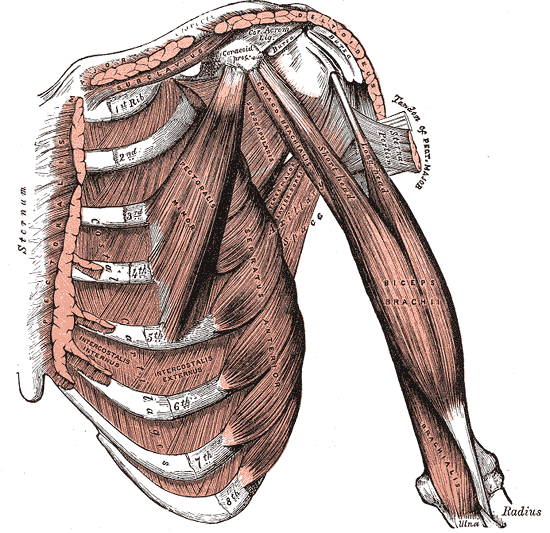
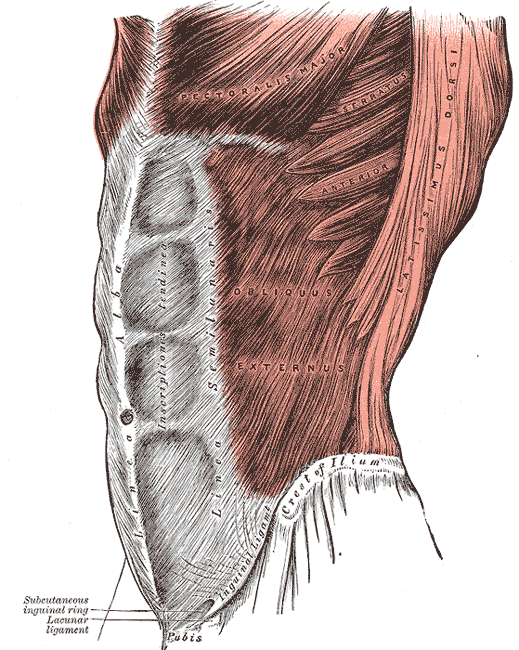
起始
第1~9肋骨
停止
・上部:肩甲骨上角の肋骨面
・中部:肩甲骨内側縁の肋骨面
・下部:肩甲骨下角および内側縁の肋骨面
作用
・前鋸筋全体:肩甲骨を前外方に引く、上肢帯が固定されていれば肋骨の挙上(吸気の補助)
・下部:肩甲骨を回転させ、その下角を前外側に引く(関節窩を上方に回転させる、上腕の90度以上の挙上を可能にする)
・上部:挙上した上腕を下げる(下部筋束に対して拮抗)
神経支配
長胸神経(C5~C7)
コメント
前鋸筋の「鋸」は「のこぎり」を示す漢字です。
ノコギリのギザギザのように、前鋸筋がそれぞれの肋骨に付着している様子が見えたのが由来でしょう。
前鋸筋の名前がよく聞かれるのが、「立甲」と呼ばれる状態にする場合です。
立甲とは何かというと、文字通り肩甲骨が背中に対して立ち上がってくることです。
人によって、どれくらい立ち上がったら立甲と呼ぶのかは差がありますが、だいたい30〜50度くらいが基準になるようです。
「立甲すると何がいいのか?」
「立甲」と検索すれば、色々情報は出てきます。
もっともわかりやすいメリットは、「肩甲骨が動きやすくなる」ということです。
別の記事でも書いてたりしますが、肩甲骨から腕を動かすことで、肩周りの筋肉の負担を和らげることができるのです。
もうちょっと難しい話をすると、腕と肩甲骨を適切な状態で連結して動かすことで、腕の骨から肩甲骨にかけての骨をうまく使った力の伝え方、身体の支え方ができるようになるので、武道やスポーツなどで効率的な身体の使い方ができるようになったりします。
そもそも、早く走ることができる動物は肩甲骨が立甲しているように見えます。
そして、肩甲骨と腕の骨が連結して動きます。

チーターなんかはそもそもの構造が肩甲骨が身体の側面にくる構造なので、自然と立甲しやすいということもあるのですけどね。
猿やゴリラのように人間に近い構造をしている動物は、肩甲骨の基本配置が背中側になっていますが、それでも4足で移動する際は立甲しているように見受けられます。

腕の骨から肩甲骨まで一体となって杖のように身体を支えることができているので、力んでいる様子に見えないですよね。
肩甲骨が背中側にあることで、腕を特に横側に広い範囲で使うことができます。
木に登ったり、道具を使ったりするような場合には、この方が便利なわけです。
ただ、人間は普段の生活で立甲させる必要性がほとんどないので、このように肩甲骨を立てて使うことは苦手になってしまいました。
それどころか、肩甲骨を動かすということすら苦手になっています。
肩甲骨を動かさないので、肩甲骨の周りの筋肉がガチガチに固まってしまっているのです。
特に、肩甲骨が肋骨にへばりつくようになって固まっていると、本当に動きません。
だからこそ、立甲のメリットは、まず肩甲骨が動くようになることなのです。
よく言われるようになった「肩甲骨はがし」をするようなものだと思ってもらえればいいです。
ここでは、立甲がメインの話ではないので、簡単なやり方を伝えるにとどめておきます。
まずは四つん這いの状態で肘は伸ばして置いてください。
その状態で、肩甲骨から背骨を離すように、グッと胸を下げます。
そうすると、肩甲骨が中央に寄った状態になります。
そこから、少しづつゆっくりと肩甲骨を開いていき(肩甲骨を開くがわからなければ、ゆっくりと手で床を押していってください)、前鋸筋に力を入れていきます。
そして、前鋸筋に力が入っているのがもっとも感じやすいところ、胸の筋肉(大胸筋)に力が強く入る手前、で止めてやれば立甲になっています。
ポイントは、前鋸筋で肩甲骨を開こうとすると同時に、胸を下に下げ(背骨や肋骨を肩甲骨から遠ざける)ようとすることでしょうか。
うまくできていれば、肩甲骨と背骨をつなぐ筋肉(菱形筋など)にストレッチ感を感じることができるでしょう。
ほとんど立甲の話になってしまいましたが、前鋸筋が吸気の補助をしているのも見逃せないポイントです。
ただし、肩甲骨の位置が安定していないと、肋骨側を動かすことはできません。
なので、姿勢改善で肩甲骨を良い位置を安定させることは、呼吸のしやすさにもつながります。
最後に、本当にちなみに話になってしまうのですが、僕がこのサイトやメルマガで「背中の筋肉」という時は、その中に結構この前鋸筋が含まれていたりします。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。