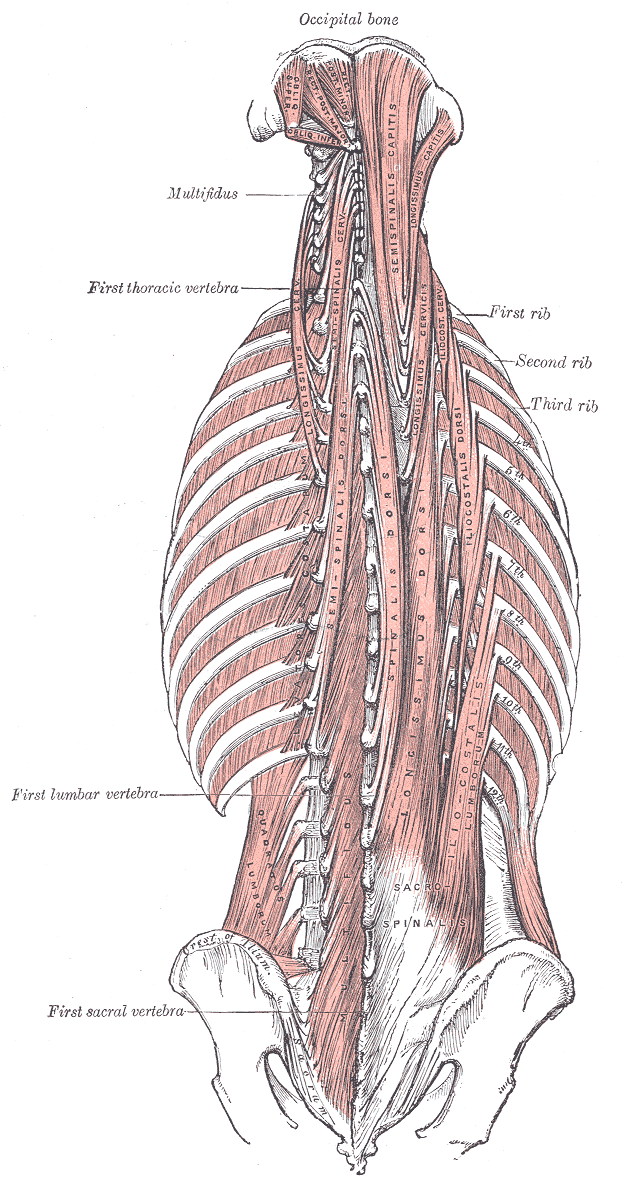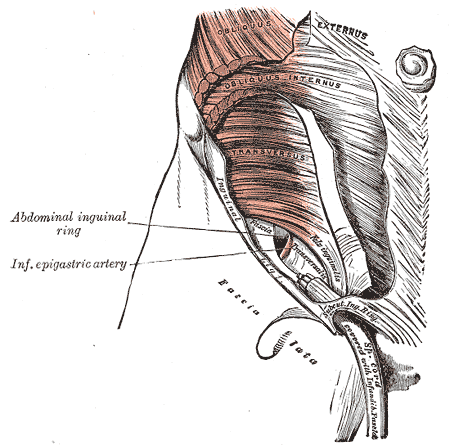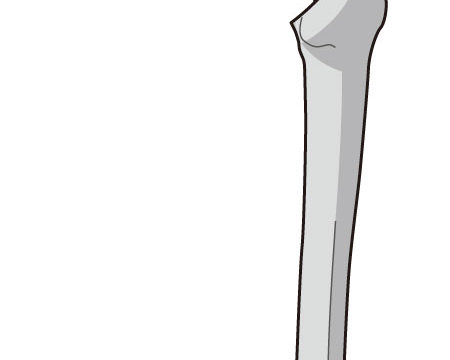力とは
物が変形したり、動く速度が変わったりするのは、物に力がはたらいたからです。
身体が動くのももちろん力が働いているからです。
何も力が加わらなければ変形もしないし、速度も変わりません。
また、変形しなくても、石が地面の上に置かれていて静止している時でも、重力という力が石にはたらいています。
力とはいっても、物理的な力には様々な種類があります。
力を種類別に分類すると、重力や、人間の筋肉による力や、ひもが物を引っ張る時の張力や、物を引きずる時に感じる摩擦力や、水の中の物体を持ち上げようとする浮力や、ばねによる弾性力や、荷電粒子の間にはたらく電気力(クーロン力)や、磁石同士が引き合う磁気力などがあります。
力にはいろいろな名前が付いていますが、そのどれもが元を辿ると重力か電磁気力の2種類の力に行き着きます。
人間の筋肉による力も、脳内で発生した電気信号を神経細胞が腕の筋肉に伝え、筋肉細胞を構成する分子たちが電気をやりとりして、筋肉を縮めたり伸ばしたりするのです。
張力に関しても、ロープを構成する綿や化学繊維の分子が分子間力によって、外から引っ張られる力に対抗しているのです。分子間力の元は電磁気力です。摩擦力と浮力の元は重力ですし、弾性力の元は電磁気力です。
いろいろな力があると言っても、おおもとは重力か電磁気力の2種類であり、さまざまな場面によって張力、摩擦力、浮力、弾性力などと名前を付けて呼んでいるのです。
このあたりは後ほど簡単に説明しますね。
力の単位には[N]ニュートンが用いられます。
あの有名なニュートンの名前からきています。
1[N] は質量1[kg] の物体に1[m/s2] の加速度を生じさせるような力と定義されています。
地球は重力という力によって地球上のあらゆる物体を引っ張っています。
そしてそのときの加速度は9.8[m/s2]です。
ということは、1[kg] の物体にかかる重力という力の大きさは9.8[N]ということになります。
重力が働いているということは、常に加速度は9.8[m/s2]の鉛直下向きの力が加えられ続けているということです。
だからこそ、身体の使い方を考える上で重力は無視できません。
力というものは、いろんな方向に働きます。
その際、同じ方向に向き合うことがあれば、逆向きにもなります。
例えば、2Nの力と2Nの力を合わせれば4Nの力になります。
これを力の合成といい、合わせられた力を合力といいます。
同じ作用線上にあって同じ方向を向いている力同士の合成なら問題ありません。
違う方向を向いている場合は三角関数の知識で考えることになります。
力の合成の反対が力の分解になります。
分解した力を分力といいます。
物体に複数の力が作用しているのに、物体が動かない場合、これらの力はつり合っているといいます。
これは複数の力の合力が0になっているからで、この状態を力のつり合いといいます。
最初の方で、石は動かないけど重力は作用しているという話をしましたが、石が動かないのでは重力と何らかの力がつり合っているからです。
また、力のつり合いは物体が動かない場合だけでなく、等速度運動している場合も力がつり合っているといえます。
力が作用しなければ、物体に変化はない。
この法則を慣性の法則といいます。
自動車でいうとある程度の速度まで加速した後、アクセルから足を離して惰性で走っている状況ですね。
もちろん、細かく見れば、車の部品同士の摩擦や地面との摩擦、車の空気抵抗などによって徐々にスピードは落ちていきますが、アクセルで加速しなくても、車は走ります。
複数の力がはたらいているのに物体の運動状態が変化しないような場合、力がつり合っているというのです。
力の種類
身体の使い方を考える上でよく出てくる種類の力についてお伝えします。
弾性力とは、力を加えられた物体が元に戻ろうとする力をいいます。
たとえば、ばねを引き伸ばしたり、押し縮めようとすると元の自然の長さに戻ろうとしますね。
弾性力は、作用・反作用の法則にのっとった力です。引っ張ろうとすると引っ張り返され、押し縮めようとすると押し戻されます。
垂直抗力とは、地面が重りを押し返す力、すなわち、物体が平面に接触しているとき、平面が物体を垂直に押し返す力のことをいいます。
細かくみれば(伸びが観測できないほど小さい)弾性力、とも考えることができます。
ちなみに、垂直抗力は重力に対する反作用ではありません。
重力は物体全体にかかる力です。
そして、垂直抗力は重力と同じ大きさの力で、物体が下の物体を押す力の反作用です。
つまり、垂直抗力は面に対する力なのです。
ややこしいですね。
重力に対する反作用は引力です。
地球の引力と僕たちが生じせている引力とが作用反作用の関係にあるのです。
僕もこの点には気をつけないといけないなと思います。
張力とは、ロープや糸やワイヤーをピンと張った時に引きちぎられないように踏ん張る力のことをいいます。
張力は、引っ張られている物質に対してあらゆる部分に同じ大きさの力が働いています。
摩擦力とは、二つの物体が接触している際に、その接触面に平行な方向に働く力のことをいいます。
たとえば、つるつるのなめらかな面(たとえばスケートリンク)の上に置かれた物体は小さな力で動かすことができます。
一方、ざらざらのあらい面(たとえばコンクリート)の上に置かれた物体は大きな力でないと動かすことができません。
これは動かそうとする向きと逆向きに力がはたらいて邪魔をするためなんです。つまり、物体の下面と床面とのこすれ合いによるものです。
摩擦力はこのこすれ合って邪魔する力のことをいいます。
摩擦力は動かそうとする向きと逆向きにはたらきます。
凸凹がするどく突き出ているほど摩擦力は大きくなります。
物体が重いほど摩擦力が大きくなります。
床面に押し付ける力が強いほど摩擦力が大きくなるのです。
圧力とは、単位面積当たりにかかる垂直の力のことをいいます。「垂直の力」というのは、たとえ面に斜めに力が作用していても垂直成分だけを考えるということです(力の分解を行う)。
「面積にかかる力」といったら一般に垂直にかかる力のことをいいます。同じ面積に、より大きな力がかかれば圧力は大きくなりますし、同じ面積により小さな力がかかれば圧力は小さくなります。
同じ力でもより大きな面積にかかれば圧力は小さくなりますし、同じ力でもより小さな面積にかかれば圧力は大きくなります。
骨の積み木が積みあがったときに、足裏にかかる荷重が重く感じるのは、圧力が大きくなるからです。
圧力 p の単位はパスカル[Pa](17世紀のフランスの物理学者であり哲学者のPascalより。量記号としての p は小文字で書くことが多いようです。)であり、1[m²]当たり1[N]の力がはたらくときの圧力が1[Pa]と定義されています。
1[Pa]=1[N/m²]です。100[Pa]を1ヘクトパスカル[hPa]といいます。
ヘクトは100倍という意味です。海面での大気圧の標準値は1013[hPa]で、これを1気圧[atm](アトム、大気atmosphereから)といいます。
1[atm]=1013[hPa]=101300[Pa]=1.013×105[Pa]です。
パスカルの定理とは、容器に閉じ込められた流体に圧力を加えて容器の体積を縮めようとすると、「その圧力は流体全体に等しく」伝わり、「あらゆる面」に「垂直」に作用することをいいます。
流体とは、物質の状態である、固体、液体、気体のうち、液体と気体を指します。
自由に形を変えられるのが流体です。
流体といってもここで考える流体は流れている流体(水流や風など)ではなく静止している流体です。
圧力が「あらゆる面」に作用する理由は、流体中の分子というのはあらゆる方向に均等に揺れているからです。
これをブラウン運動といいます。19世紀前半、イギリスの植物学者ロバート・ブラウンが発見しました。
分子はあらゆる方向に均等に揺れることにより、面にぶつかるときの角度もあらゆる角度でぶつかり、その角度を平均すると垂直になるのです。
水圧とは、容器の中の水が容器側面や底面を押す、また、水中に物体があれば物体を押す、さらに、水分子同士が押し合うときの水の圧力のことをいいます。水圧の大きさは高さのみにより、水圧はあらゆるものに対して垂直にはたらく、ということがいえます。
浮力とは、水中にある物体を浮き上がらせようとする力のことをいいます。浮力は、水中の物体の上面を押す力より下面を押す力の方が大きいことにより生じます。
また、浮力は流体中において、深さによる圧力の差によって生じる鉛直上向き(=重力と反対方向)の力になります。
「浮力の大きさは、物体が排除した流体の重さに等しい」とする原理をアルキメデスの原理といいます。
力についてダダーっと書きましたが、別個に力について記事にしていたりするので、詳しく見たい人はそちらを参考にしてみてください。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。