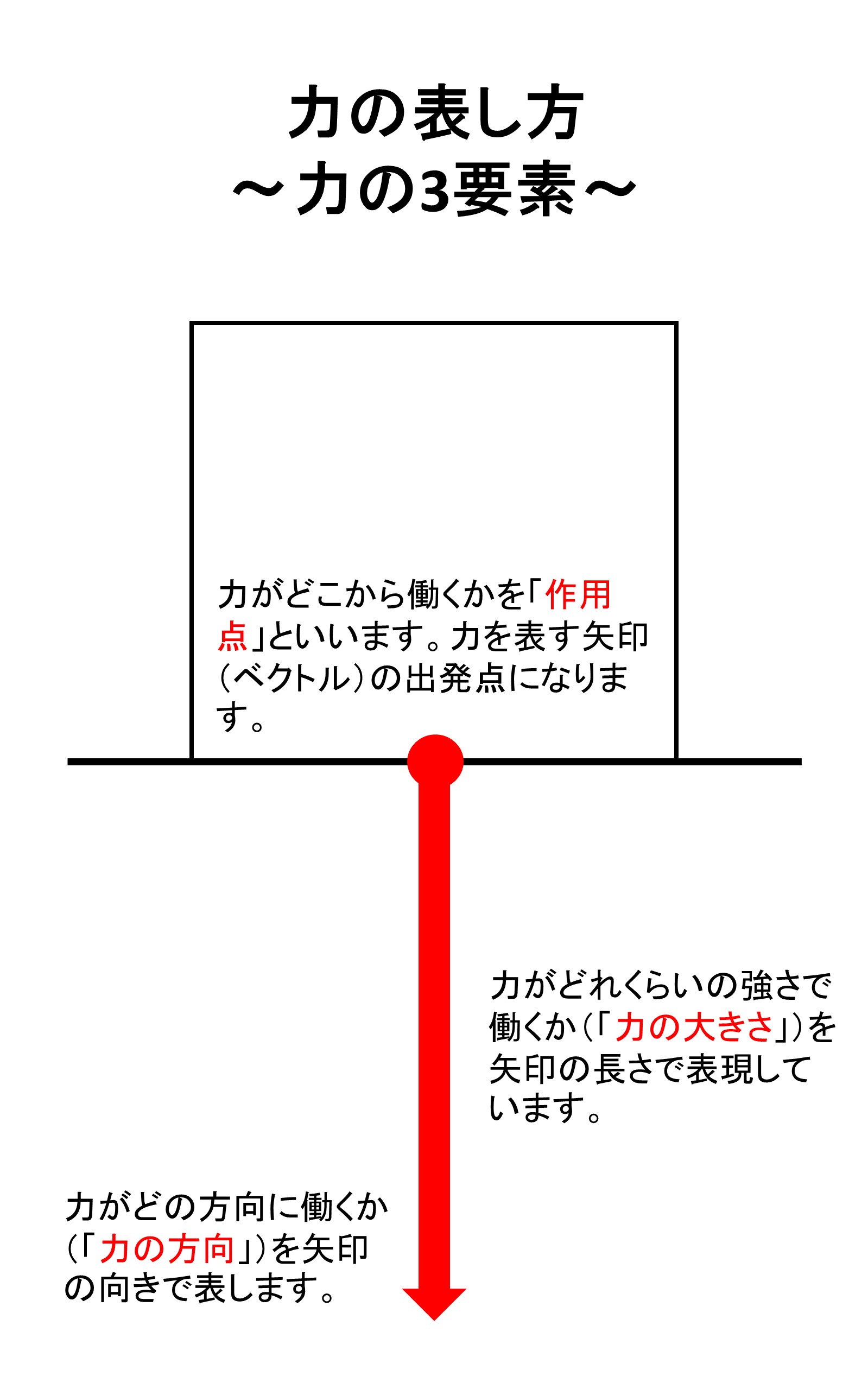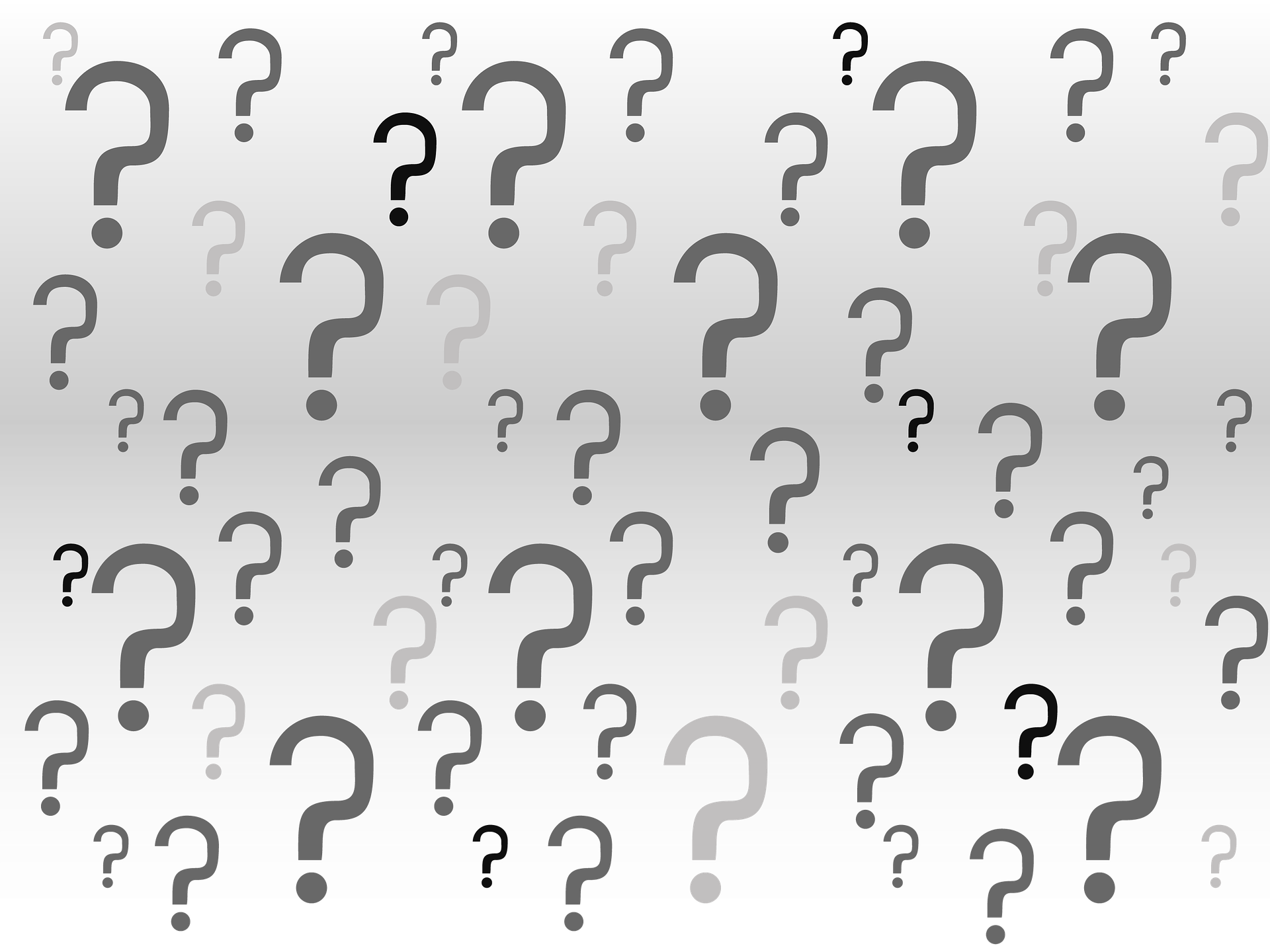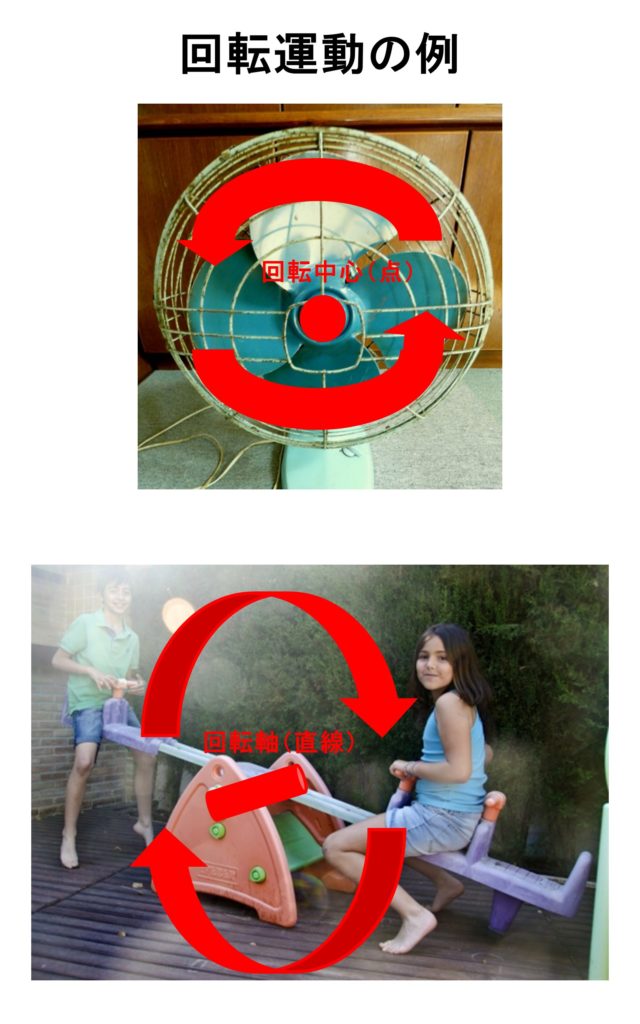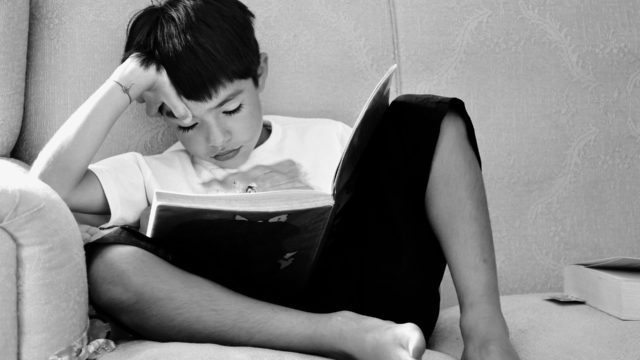「学ぶ」は元々「まねぶ」と言われていて、「真似る」と同じ語源から派生してきたといわれています。
昔は、「学ぶ」こととは「真似る」ことだったんですね。
それがよく表れているのが職人の世界です。
職人の世界では、テレビでもたびたび取り上げられるように、長い下積み期間があります。
その下積みの間に師匠の技を見て盗みながら、真似していって練習し己の技を磨いていくのです。
師匠が事細かに教えるということがまれなのです。
例えば、寿司職人の世界では、人前で寿司を握るようになるのに、5年以上かかるのは普通なんだそうです。
5年ってかなり長いですよ。
そんな中、出現してきて話題になったのが3ヶ月で寿司職人になれる学校です。
このときは大きな議論が起こったのを覚えています。
下積み支持派と学校支持派の議論ですね。
今までの寿司職人も長い下積みをしてきた伝統があるし、盗み見て考えることで、職人として成長すると考えているのが下積み支持派なのでしょう。
長年の経験でしか培われないものがあると考えているので、3ヶ月という短期間にちょろっと勉強したくらいの新参者に何ができようか、というところでしょうか。
一方、学校支持派は、「言えばわかることを見ながら学んでいくというのは効率が悪い。さっさと教えてあげればええやん?」というのが根本の考えです。
僕は、基本的には学校支持派に賛成です。
確かに、見て真似て学ぶ下積みのように、「真似て学ぶ」というのは、とても大事なことだと思います。
ただ、単純に真似するだけでは技術が向上しづらいと僕は思います。
師匠の真似をする中で、
「なぜそのようなことをするのか」
「なぜそのようにするのか」
を考えていかないといけません。
師匠の行動は結果でしかありません。
本当に見ていかなければならないのは、師匠が現在のように至った過程、師匠が何を考えてそのような行動をするに至ったかなのです。
そこに本質があるんですね。
この過程の部分、本質の部分は言葉で伝えられるものも多いのです。
なので、学校支持派のように、言葉で伝えられるものは、伝えて教えてしまったほうが、確実に上達が早いです。
だから、僕は基本的には学校支持派の意見に賛成です。
ただ、全面的に学校での学びだけでいいかというと、それも違うと思います。
どうしても言葉だけで伝えられない部分があるんですね。
例えば、僕は自分の整体の感覚的な部分をいまだにうまく言語化できません。
やっていることは、「身体を動かしたときに邪魔になるところを取り除く」ということに尽きます。
ただ、邪魔している部分がなぜわかるかといわれれば、理論的にわかる部分もあるけども、究極的には感覚的なものなので、言葉で伝えようがないのです。
身体の使い方に関していえば、その9割くらいは言語化できます。
この言語化できる部分を理解した上で真似していけば、
「なぜそのようなことをするのか」
「なぜそのようにするのか」
ということを理解するための土台の知識となってくれるのです。
なので、下積みがいいか学校がいいかの2択ではなく、いい塩梅のバランスで両立するのがベストだと思います。
身体の使い方にしても何にしても本質を押さえた上での真似こそがもっとも早く上達する方法だと僕は思います。
追伸
ちょっと話反れるかもしれないですけど、ディズニー映画の「アナと雪の女王」の主人公エルサの声って世界のどの言語でも同じ人の声に聞こえるように、似た声の人を声優としてキャスティングしてるんですって。
セリフでの口の動きも、国の違いで違和感がないように、翻訳を工夫しているそうです。
すごいこだわりですね。
以前「関ジャム」という日曜の夜にやっている音楽番組のディズニー音楽を取り扱っていて知りました。
僕は音楽にはセンスも興味なかったですが、この番組は音楽を理論的にしかもおもしろおかしく解説してくれるのでおすすめです。
芸術というあいまいなものはどうしても理解しづらいので、理論を解説してくれると入っていきやすいし、僕もある意味あいまいなものを理論にしようとする仕事ではあるので、勉強させてもらってます。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
電子書籍とメールセミナーを読んでみる
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。