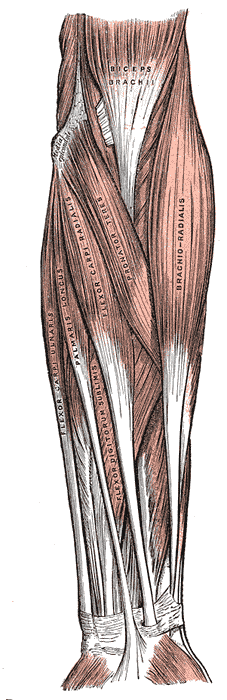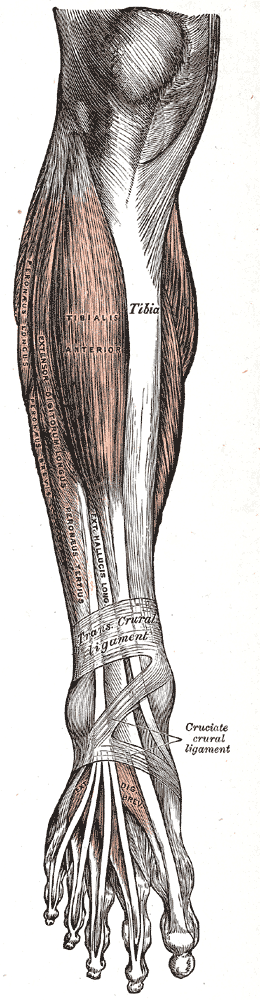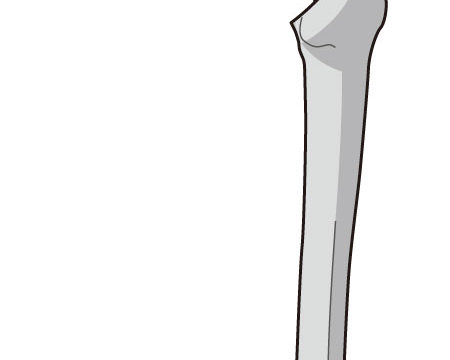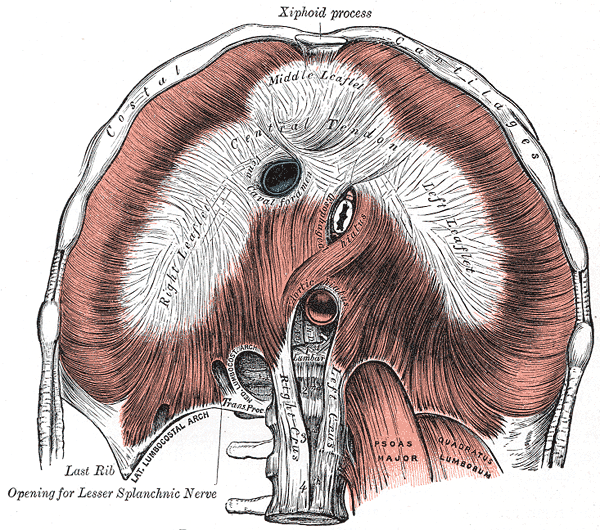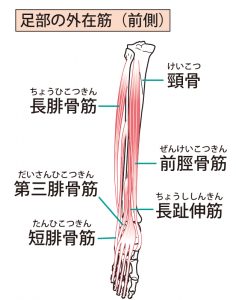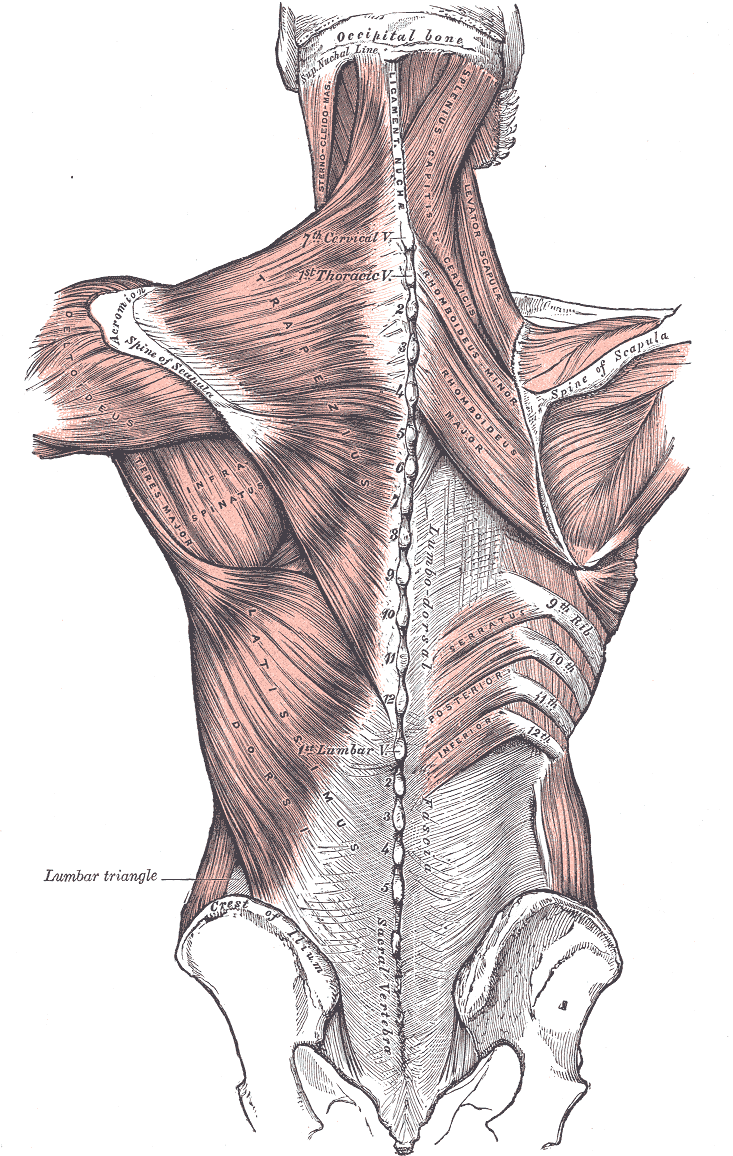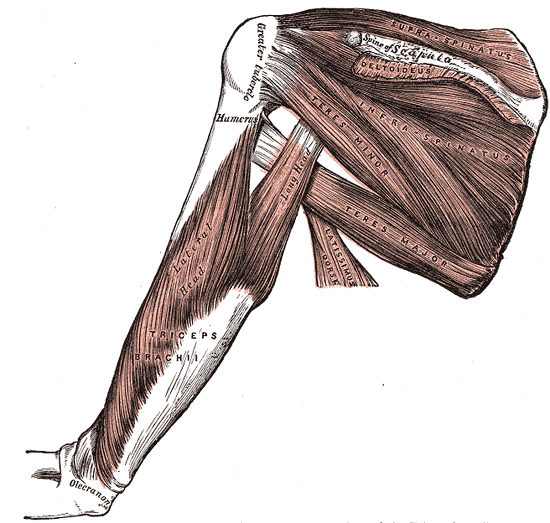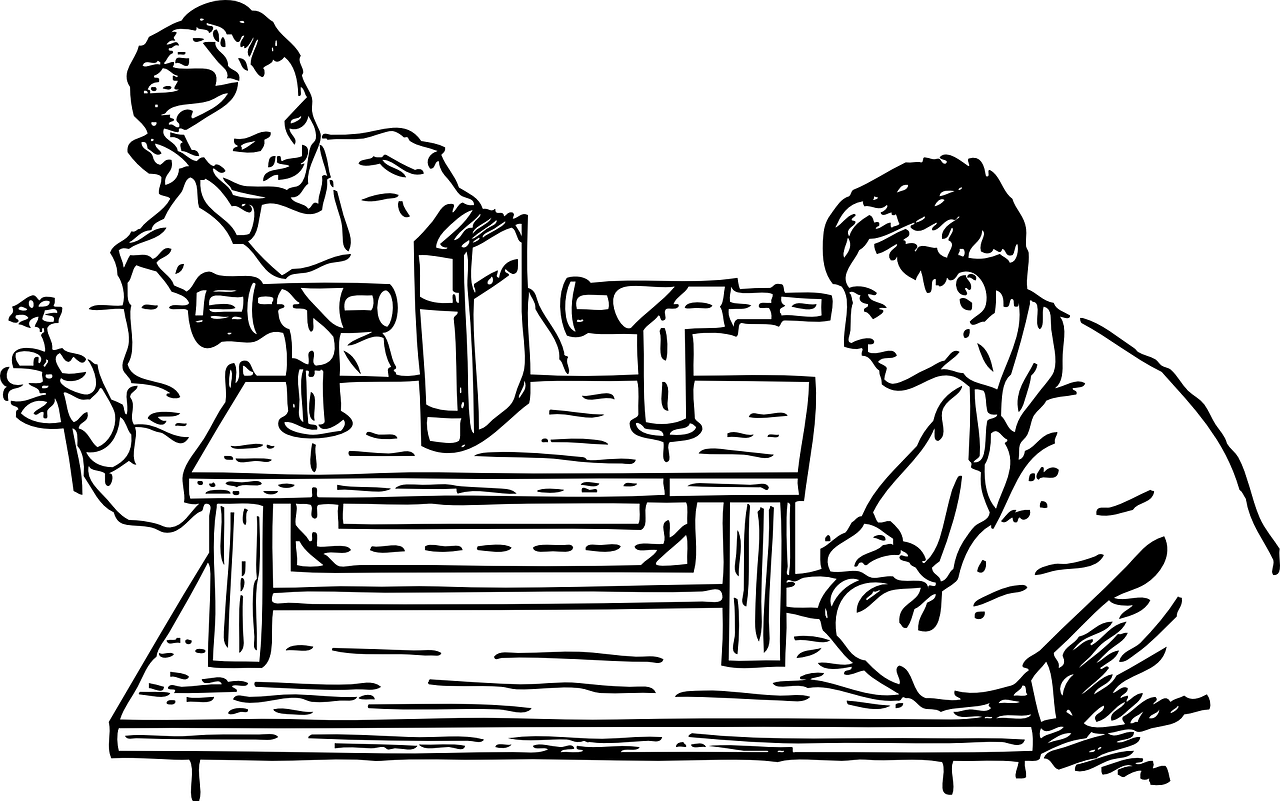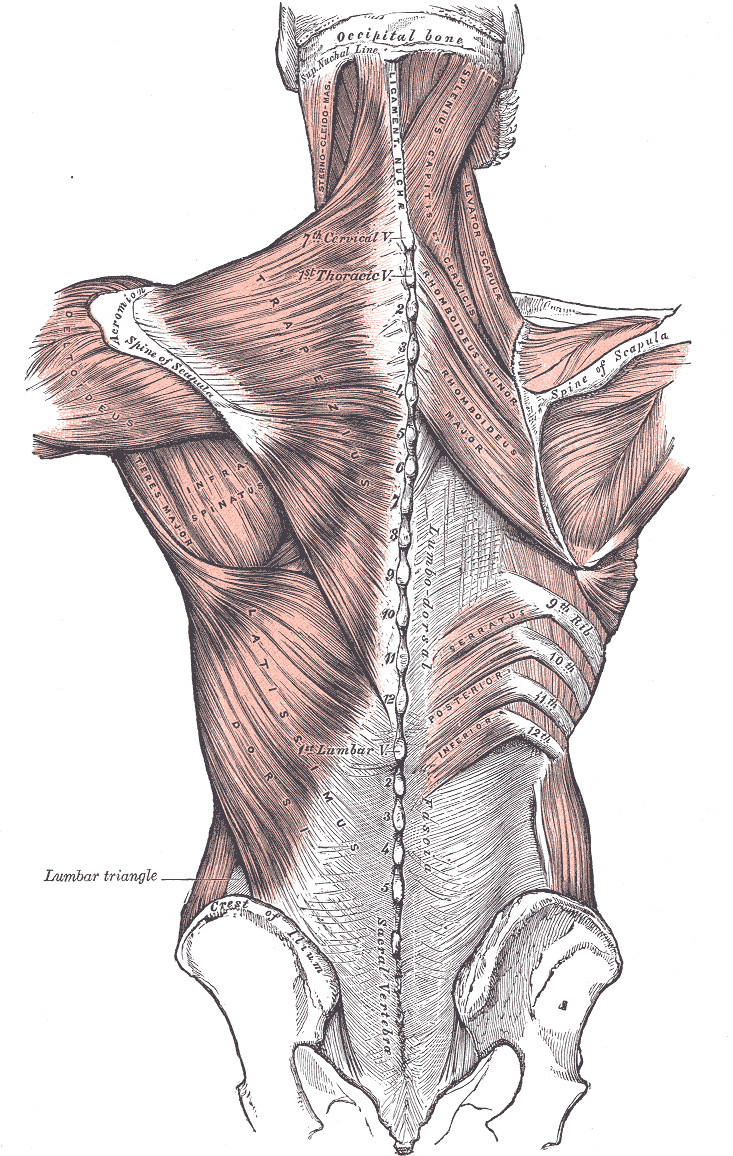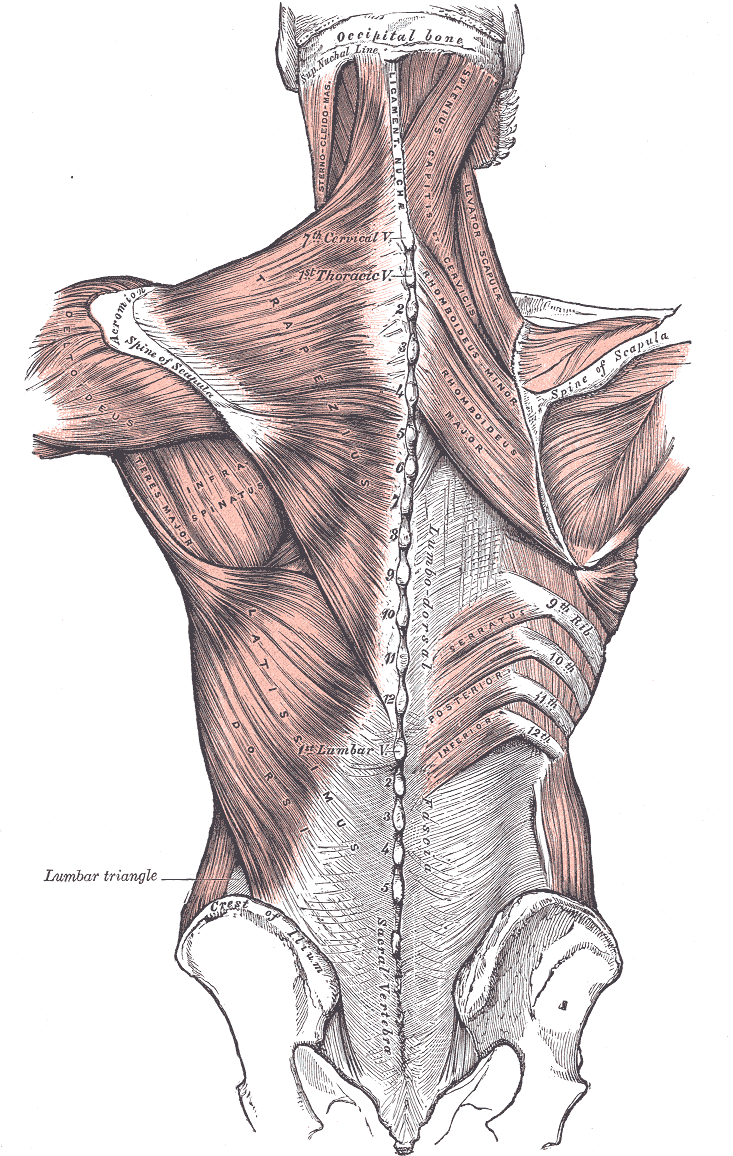脊柱起立筋は聞いたことありますかね?
脊柱起立筋は、文字通り「背骨を立てておく」筋肉です。
二足直立の姿勢を保つために大きな貢献をしてくれている筋肉です。
背中を見たときに盛り上がる2つの山、あれが脊柱起立筋です。
脊柱起立筋は、1つの筋肉ではなく、腸肋筋、最長筋、棘筋で構成されています。
以下、それぞれの筋肉についてお伝えしていきます。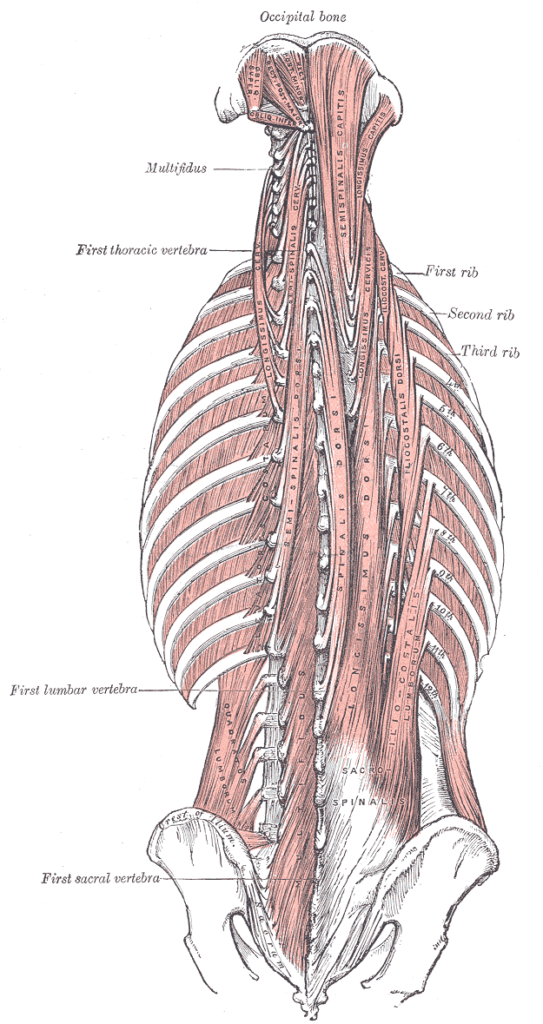
腸肋筋
起始
・腰腸肋筋(Iliocostalis lumborum):仙骨、腸骨稜、胸腰筋膜(浅葉)
・胸腸肋筋(Iliocostalis thoracis):第3~12肋骨
・頸腸肋筋(Iliocostalis cervicis):第3~7肋骨
停止
・腰腸肋筋:第6~12肋骨、腸腰筋膜の中葉、上位腰椎の肋骨突起
・胸腸肋筋:第1~6肋骨
・頸腸肋筋:第4~6頸椎の横突起
作用
両側が収縮:両側が収縮すると脊柱を伸展させる。
片側が収縮:脊柱を同じ側に屈曲する。
神経支配
第8頸神経~第1腰神経の各後枝の外側枝
コメント
脊柱起立筋の中で、外側に位置します。
名前の通り、全体としては腸骨と肋骨をつないでますね。
最長筋
起始
・胸最長筋(Longissimus thoracis):仙骨、腸骨稜(腸肋筋と同じ筋膜を介する)、腰椎の棘突起、下位胸椎の横突起
・頸最長筋(Longissimus cervicis):第1~6胸椎の横突起
・頭最長筋(Longissimus capitis):第1~3胸椎の横突起、第4~7頸椎の横突起と関節突起
停止
・胸最長筋:第2~12肋骨、腰椎の肋骨突起、胸椎の横突起
・頸最長筋:第2~5頸椎の横突起
・頭最長筋:側頭骨の乳様突起
作用
胸最長筋、頸最長筋:両側が収縮すると脊柱を伸展させます。片側が収縮した場合は、脊柱を同じ側に屈曲します。
頭最長筋:両側が収縮すると頭を後屈し、片側が収縮すると、頭を同じ側に屈曲、回旋します。
神経支配
第1頸神経~第5腰神経の各後枝の外側枝
コメント
脊柱起立筋の中で、腸肋筋と棘筋の中間にあります。
脊柱起立筋の中で、頭骨から骨盤まで付着している唯一の筋です。
「最長」筋という名前の通り、頭蓋骨から骨盤にわたる長い筋肉です。
胸最長筋は、名前に「胸」と入っていますが、骨盤まで付着しているので注意してください。
棘筋
起始
・胸棘筋(Spinalis thoracis):第10~12胸椎および第1~3腰椎の棘突起の外側面
・頸棘筋(Spinalis cervicis):第1~2胸椎および第5~7頸椎の棘突起
停止
・胸棘筋:第2~8胸椎の棘突起の外側面
・頸棘筋:第2~5頸椎の棘突起
作用
両側が収縮すると頸椎と胸椎を伸展させます。
片側が収縮した場合は、頸椎と胸椎を同じ側に屈曲します。
神経支配
脊髄神経の後枝
コメント
脊柱起立筋の中で、内側にあります。
「棘」筋という名前の通り、付着がすべて棘突起になっています。
線維の方向を見てみると、腸肋筋や最長筋は、背骨や肋骨を下方に押し付けるような支持の仕方でしたが、棘筋はちょっと違ってて、頸棘筋と胸棘筋、それぞれ上下に伸びる付着部の中央部に向かって背骨を引き寄せるような支持の仕方をしています。
脊柱起立筋についてのコメント
脊柱起立筋全体の特徴として、脊椎の伸展、骨盤前傾に関与します。
これらはいずれも、二足直立を支えるためになくてはならないものです。
しかも、脊柱起立筋の場合は、背骨や肋骨を1つ1つ繋ぎ合わせている上に、筋肉としても大きいので、その支持力は特に強力なものになっています。
それだけ、脊柱起立筋にかかる負担が大きいということを暗示するようです。
脊柱起立筋は、人間の柱である脊柱を支える筋肉であり、無意識で使ってしまいやすい筋肉です。
また、力の強さは、強い支持力を生み出す一方で、骨の積み木がひとたびずれてしまうと、その力が積み木をさらに崩していく方向に働くということは頭に入れておかなければなりません。
骨格筋は互いに引っ張り合うことでバランスをとっています。
この脊柱起立筋に対する負担をいかに分散させるかが、身体の使い方といっても過言ではないです。
本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう
記事を読んでいただいてありがとうございます。
僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】
ということをテーマに情報発信しています。
姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間
ずっと関わることになるものです。
なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。
姿勢次第で自分の身体に枷をかけ
身体の動きを抑え込んでしまったり
身体を痛めてしまうことがあれば、
意識せず自分自身を抑え込んでいる
枷から自分を解放し
身体を軽やかに痛みなく
思い通りに動かせることになります。
身体と心はつながっていて
不可分な関係なので、
身体の調子が悪ければ
心も当然暗くふさぎ込んで
しまうことになるし、
調子が良ければ明るく
前向きになってきます。
つまり、姿勢を改善することは、
最も簡単で確実な自己改善法なのです。
しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、
「なんとなくこうだろう」という
常識で固められてしまっています。
そのため、姿勢を良くしようと
努力しているにもかかわらず
姿勢が一向に良くならないという
状態になってしまっていることを
よく聞きます。
根本から姿勢改善するためには、
この常識から抜け出さなくては
なりません。
姿勢改善に必要なのは
「背筋を伸ばすこと」でも
「胸を張ること」でも
「筋肉をつけること」でも
「意識すること」でも
ありません。
本当に必要なのは
「姿勢の本質を理解すること」です。
そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人
が少しでも増えるように、
姿勢の本質から理解を深め改善する方法を
電子書籍にまとめました。
本来はAmazonで有料で販売しているものですが、
メルマガの中で今だけ無料で公開しています。
図を多く取り入れていて
読みやすい内容になってますので、
もし興味あれば読んでみてください。
→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる
メールアドレスを入力すれば
すぐに受け取れます。
また、メールマガジンに登録してもらった人には、
さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」
も無料でお送りしています。
書籍と合わせて読んでもらうことで、
姿勢の常識から抜け出し、
姿勢の本質への理解を一気に
深めてもらうことができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もし、この記事が役に立ったと思われたら、
下にあるボタンからSNS等でシェア
していただけるとすごく嬉しいです。